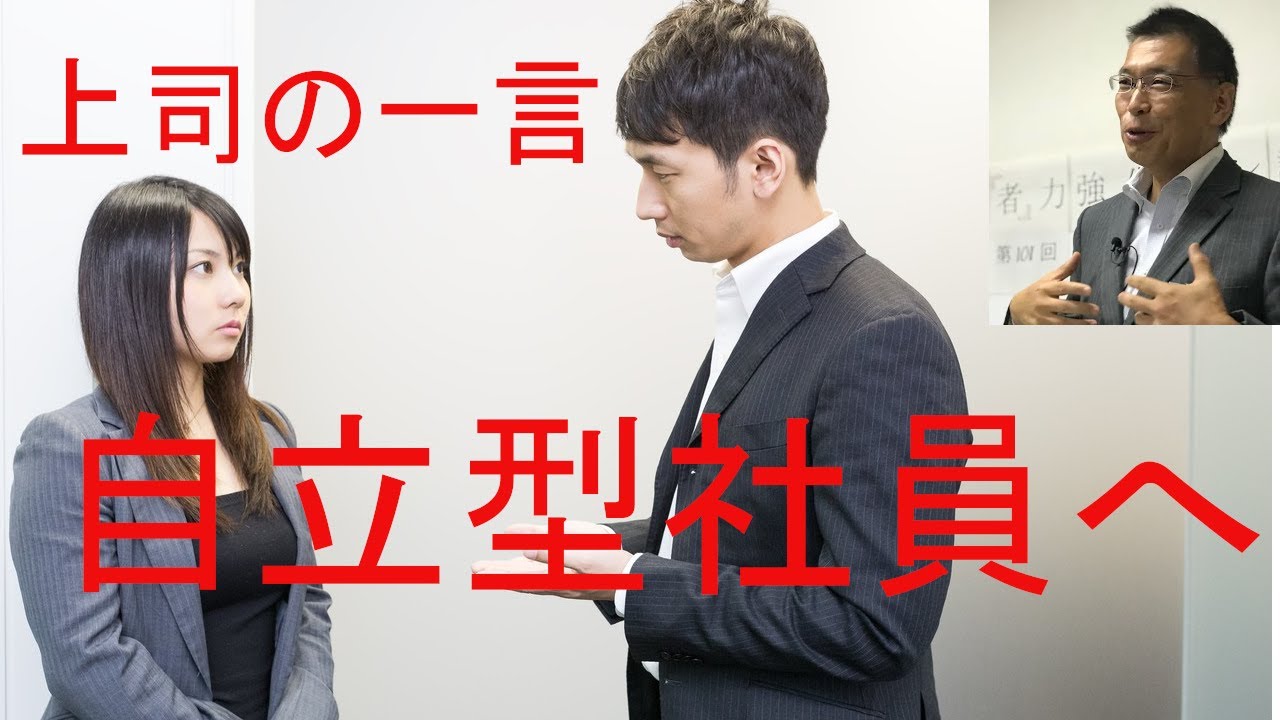職場に配属された新人が、指示待ちで困っている。
入社当時はまだしも、3か月も、半年も経っても続いている。
この様なお悩みは、よく、人事や上司の方から伺います。
ズバリ、何があればよいのでしょうか?
今回は、受け身型の人材が、自立型に自然となってしまう、
立ち位置の醸成をお伝えします。
自立型人材と、依存型人材の決定的な違いとは?

今回は新入社員の積極性ということで、一緒に考えてまいりたいと思います。
よく経営の現場を歩いてますと、現場配属されたにも関わらずですね、
とにかく新入社員が指示待ちで困ってるんだよ、という声をよく聞きます。
上長の方、あるいは、人事の方、あるいは経営者の方からですね、
この指示待ちをどうしたら、やはり変えていくことができるんだろうか?
自立型人材に、なんとか育っていってもらいたいという願いを持っておられる、
リーダーの方が、すごく、多いのかなというふうに思っております。
そこでこの自律型人材と、依存型人材、
決定的に、何が違うと皆さんは考えられるでしょうか?
働くとは、端を楽にすること
私は、まず、
この自立型と依存型ということで、
違うのは現象面から言えば、やはり、
不平不満が、依存型傾向の人はすごく多いのかなというふうに思っております。
ですから、新入社員の時に、学生から社会人になる切り替えが、やはり、できてないのかなと、
一言で言えば、やはり、
「働くとは、端を楽にすること」なんだと、
学生のときは、授業料を払う、そして社会人であれば、その、給料をもらうっていうようなね、
具体的に言えば、受益者ということで、
何かお金を払う、学生のときは払う代わりに、益となるものをもらってた、
授業でいろんな学びを教えてもらうとか、そういった部分が、学生でございました。
そして翻って社会人っていうのは、なによりも、稼いでですね、
提供する、サービスを提供する、ものづくりをしてそれを提供する、
提供者に代わっている、受益者から提供者に変わっている。
ここが、切り替わってないがためにですね、
何をしてもらっても、当たり前、何をやってもらっても当たり前、教えてもらっても当たり前、
っていう風な気持ちからなかなか抜け出せない、だからこそ受け身であり、待ちの姿勢で、常に周りが何かやってくれることを、期待をしている部分があるんでしょはないんでしょうか。
だからこそ、こういう依存型のスタッフ、社員はですね、不平不満を常に感じている、あれをしてくれないっていう、くれない族になったり、
不平不満が常に、くすぶってて、挙句の果ては、辞めてしまうというところではないでしょう
か?
だからこそ、まず1番目には、「働くとは端を楽にすることなんだ」というこの考え方をですね、新入社員と共有していくと、これをご提案をさせていただきます。
質問も、新入社員の大事な仕事
そして2つめはですね、これは現場での具体的な場面ですけれども、やはり、報連相っていうことは、よく報連相ができる人材を育ててもらいたいという声を、よく聞くんですけども、
私はそれ以上に大事なのは、指示受け、このタイミング、この瞬間かなと思っています。
報連相っていうのは終わってから、報連相ですけども、指示受けっていうのは、スタート段階なんですね。
スタート段階に、どれだけ新入社員と、我々、上長が、
きっちりと握ることができるのか、ということが大事ではないでしょうか。
よく、新入社員に指示を出して、「はい、わかりました」っていう元気なのはいいんですけどね、
「何が分かったの?」って言ったら、しどろもどろになる、そんな新入社員、あるいは新人を目の当たりしたことは皆さんも、なかったでしょうか?
だからこそ、この指示待ち、指示を出した時に、新入社員が指示を受けた時に、
どういう姿勢が大事かというと、やはり、
「質問も新人の一つの大事な仕事なんだと」
もう一度、いいます。
「質問も新入社員の大事な仕事なんだ」ということをですね、
やはり共有しておくことが大事ではないでしょうか。
もちろん上長が、甘えてですね、「これやっとけ」っていうような形でですね、
大きな、不明確な、そういった指示を出すということに、あまんじてては、もちろんダメですけれども、
やはり上司とて、人間でございますので、明確な、バタバタしててですね、言い忘れたりとか、言い漏らしたりとか、そういうこともあります、だからこそ新入社員と一緒に、
明確で的確な指示であり、依頼をですね、一緒に作っていくっていうようなスタンスを、育んでいくことが、大事ではないでしょうか。
ですので、2番目の提案としては、指示受け時にですね、
「質問も新入社員の大事な1つの仕事なんだ」
「これはいつまでにやればいいでしょうか?」
「これはどういうようなゴールイメージでしょうか?」
「これはステップとしては、今、ご指示いただいた部分で言えば、3つあったと思いますけど、これで間違いないでしょうか?」とか、
そういうような、確認あるいは質問、これをする事をですね、新入社員と一緒に、
上長は作っていくということが大事ではないでしょうか。
そういうことで、2つ申し上げました、働くとは端を楽にすること、
そして指示受け時に、質問も新人の大事な1つの仕事じゃないかということをですね、
ぜひ2つ、取り組む中で、この依存型傾向の社員ではなくて、
自立型の社員を一緒に作ってまいりましょう。
はい今日は以上でございます。今日はここまでです。

-

新人若手力セミナー【2025年】
2泊3日宿泊徹底型・社員教育セミナー セミナーのご案内 新人若手力セミナーとは、小さくとも強い企業として若い力を活かした社内変革を生み出すための取り組みです。 セミナーでは、各社の新入社員と若手社員で ...
続きを見る
まとめ
働くとは、端を楽にすること
- 学生から社会人:受益者から提供者へ
- 授業料を払うから、給料をいただくへ
- 自分の当たり前病に気づく(やってくれて当たり前、教えてくれて当たり前)
- 依存型は、ありがとうという意識が少なく、これが足りない、あれが足りないと不平不満が多い
- 依存型は、~してくれないという「くれない病」発症
指示受け時に、質問も新人の1つの仕事
- 「はい、わかりました」と、返事だけはいい部下には注意
- 上司や先輩が全て正しいわけではない、ましてや、いつでも的確でもない、指示や依頼を出せるとは限らない
- 報連相も大事だが、そもそも指示受けができていない(スタート段階でピンボケの可能性)
- 当然、仕事の出来栄えは期待のものと、離れがち
自立型人材が育成される、あなたへの問いかけ

- 依存型人材と自立型人材、何が違う?(現在地の確認)
- 自立型で居ることの新人のメリットは?
YouTubeでも詳しく解説しています
新入社員の育成シリーズ
-

辞めない新入社員が、研修で身につけた働くスタンス(始めに) vol.1
新入社員が辞めてしまった!!あれだけ心血を注ぎ、採用、内定、現場配属と、大切に育んできたのに、、、。 今こそ切り替えていきましょう! さぁこれから一緒に、新人が身につけると辞めない視点を出し合っていき ...
続きを見る
-

辞めない新入社員が、研修で身につけた働くスタンス(給料とは?) vol.2
お給料って、あなたにとってどの様なもの? 嬉しい! やったぁ! もっと欲しい、もらうもの、振り込まれてくるもの、渡すもの、、、。 生活や家計を支え、かけがいのないものであることは間違いありません。 そ ...
続きを見る
-

辞めない新入社員が、研修で身につけた不安や失敗に負けないこころ vol.3
不安や失敗に立ち向かう、強い人材を育てるにはどうすればいいか? チャレンジする人、挑戦する人欲しいですよね。 「うまくできるのか?」「やってしまった!」と、 頭を抱えてしまう時もあるでしょう。 慣れな ...
続きを見る
-

できる新入社員を育てるために、仕事での時間の使い方が変わる上司の2つの言葉 vol.4
日々成長し、できる人材を、どの様に育てるか? いいものもってるけど、なかなか育っていかない。いつも時間に追われている。頑張っているのに、成果に結び付いていない。今回は、時間を味方につけ、 成果や成 ...
続きを見る
-

新入社員が人間関係に不安を感じない、上司からの声掛け vol.5
新人の多くが抱く不安って、何だと思われますか? 職場にうまく溶け込めるだろうか。 上司や先輩と馴染んでいけるだろうか。 といった人間関係にまつわるものが多いように感じます。 そこで、われわれリーダーは ...
続きを見る
-

辞めない新入社員が「不満は自分がつくっているかも?」と気づく上司からの一言 vol.7
新人の不安や不満にどの様に向き合っていますか? 新人が抱える不安、それが高じて不満になり、 退職に至るという流れがあります。 上司への不満、労働条件の不満、会社の将来性への不満等々。 これを低減するに ...
続きを見る