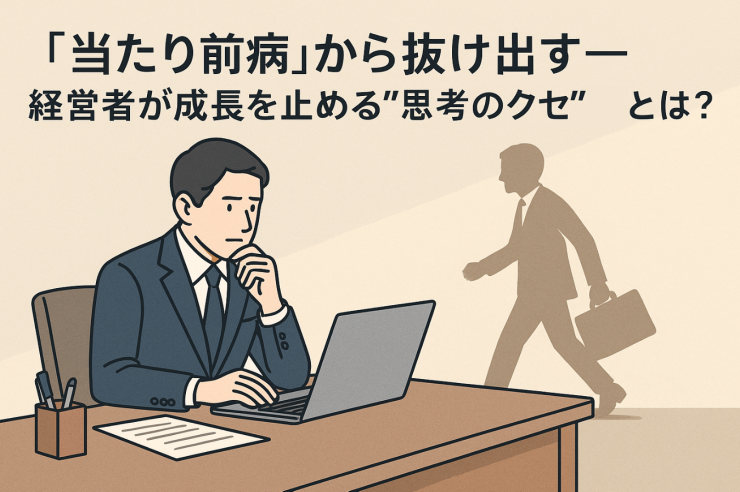【当たり前病】
これまでやってきたこと
信じてきたこと
ココに疑いをもつって
簡単なようで意外に、、、
「ムズカシイよねぇ」という口ぐが
思わず出てスルーしてしまう
自分のあたり前は
無色・無臭・透明
正体がつかみづらく
行動変容が進まない
こんな時オススメは
『歯ごたえがある』
からトライ— ふさぽ@経営者 (@future_support) November 4, 2025
経営者を蝕む「当たり前病」とは何か?
無色・無臭・透明の正体を見極める
「当たり前病」という言葉を聞くと、多くの経営者が「自分には関係ない」と感じがちです。しかし、この病の厄介なところは、まさに“自覚しにくい”という点にあります。無色・無臭・透明──それが「当たり前病」の正体です。つまり、自分では気づかないうちに、思考や行動が固定化され、変化への感度が鈍っていくのです。
経営の現場でよく見られるのが、「うちはこのやり方でやってきた」「これが一番効率的だ」という口ぐせ。かつての成功体験が、そのまま“正解”として塗り固められていく過程です。もちろん、過去の積み重ねには価値があります。しかし、その「過去の正解」が未来を制約する“無意識の壁”となることがあるのです。
私自身も、創業当初に同じ経験をしました。ある研修プログラムを数年続けるうち、参加者の反応が鈍くなってきた。改善の余地を探していた時、スタッフから「水野さん、それって“昔の当たり前”になってませんか?」と指摘されたのです。その一言が胸に刺さり、ハッとしました。自分が信じてきたやり方こそ、最も見直すべき“透明の壁”だったのです。
経営者に必要なのは、自らの「当たり前」を写し出す“鏡”を持つこと。日常の判断や言葉づかいの中に、自分の無意識の前提が潜んでいないかを見つめ直す。その一歩が、組織にも新たな風を吹き込むことにつながるのです。
「ムズカシイよねぇ」が招く思考停止の危険性
「ムズカシイよねぇ」──経営者の皆さんも、一度は口にしたことがある言葉ではないでしょうか。実はこの一言こそが、思考停止の入り口になることがあります。
「ムズカシイ」という言葉は、問題の存在を認識しているように見えて、実は“考えることをやめる”ための言葉でもあります。無意識のうちに、議論や検討を終わらせてしまう免罪符として使われるのです。特に、経営者ほど多くの課題を抱え、決断を迫られる立場にあると、心のどこかで「ここは深く掘り下げたくない」「今は触れたくない」という防衛反応が働きやすい。これが「当たり前病」の温床になります。
私が関わったある企業でも、幹部会議で新しい販路開拓の提案が出るたびに、会長が「それはムズカシイねぇ」と一言で締めてしまう場面が続いていました。提案者たちは、反論するわけでもなく、静かに引き下がる。会議後の空気には、何とも言えない“諦めの沈黙”が漂っていたのです。
この「ムズカシイよねぇ」という言葉には、挑戦を遠ざけ、現状維持を正当化する力があります。もし口から自然と出てきたら、それは「今こそ考えるべきテーマ」が目の前にあるサインです。
経営者としての真価は、「ムズカシイ」の先にある“問い”を掘り下げられるかどうかで決まります。逃げずに考え抜く力、それこそがリーダーシップの原点です。
なぜ“当たり前”が成長を止めるのか?
「成功体験」がもたらす思考の固定化
経営の世界で最も恐ろしいのは「失敗」ではなく、「成功」だと私は感じています。なぜなら、成功は人を安心させ、安心は人を鈍らせるからです。特に長く経営を続けていると、「うまくいった方法」が知らぬ間に“正解”として定着し、その延長線上でしか物事を考えられなくなってしまう。これが、思考の固定化という落とし穴です。
ある中堅製造業の経営者とお話しした際に印象的だったのが、「うちはこの商品で食べてきた」という言葉でした。確かに、その商品は会社を支えてきた功労者です。しかし市場環境が変化する中で、その“成功の形”を守り続けること自体がリスクになっていました。経営者ご自身も頭では理解していたのですが、心のどこかで“過去の成功体験”を裏切ることへの抵抗が働いていたのです。
成功体験には、“心地よい記憶”という罠があります。人は過去に努力して手に入れた成果ほど、簡単には手放せないものです。しかし、その成功体験が新しい発想や行動を阻む壁になっているとしたら、もはやそれは資産ではなく、足かせと言えるでしょう。
経営とは、常に「昨日の成功を、今日の常識にしないこと」。
時代が変わるスピードが加速している今だからこそ、経営者には“過去を更新する勇気”が求められます。新たな挑戦を前に、成功体験を一度「棚卸し」する。これは痛みを伴いますが、組織にとっては大きな再生のチャンスでもあるのです。
無意識の惰性が組織文化をつくる
経営者の「当たり前」は、いつの間にか社員の「文化」になります。つまり、経営者自身が無意識に繰り返している習慣や考え方が、組織全体に静かに染み込んでいくのです。
「いつもこうしている」「これがうちのやり方だ」。この言葉が口癖のように飛び交う会社ほど、惰性が文化化している可能性があります。怖いのは、それが“悪いこと”として認識されない点です。むしろ「安定している」「うまく回っている」と安心してしまう。しかし、経営の現場において“安定”は往々にして“停滞”の前触れなのです。
私が関わったある企業では、社内の朝礼が20年間同じ内容のまま続いていました。かつては活気づけの意味があった儀式が、今では惰性と形式だけが残り、誰も疑問を持たない。新入社員だけが心の中で「これって何のためにやってるんだろう?」と思っていたそうです。まさに、「無意識の惰性」が組織文化をつくりあげた一例です。
経営者にとって重要なのは、この“無意識の伝染力”を自覚することです。自分が変わらなければ、組織は変わらない。逆に言えば、経営者が日常の言葉や行動を見直すだけで、会社の空気は見違えるように変わるのです。
文化は「作るもの」ではなく、「にじみ出るもの」。
その源は、経営者の“当たり前”にほかなりません。
変化できない経営者の共通点
疑うことを恐れるリーダーの心理
「疑う」という言葉に、どこかネガティブな響きを感じる方は多いでしょう。特に経営者の中には、「自分が信じてやってきたことを疑うなんて」と抵抗を覚える方も少なくありません。けれども、成長を続けるリーダーほど、“疑う勇気”を持っています。
なぜなら、疑うことは「壊すこと」ではなく、「確かめること」だからです。自らの判断軸や価値観を点検し、磨き直すための作業なのです。ところが、多くのリーダーは無意識のうちに「疑う=自信がない」「信念がブレる」と結びつけてしまいがちです。その結果、変化の兆しを前にしても、“過去の自分”を守ることにエネルギーを使ってしまう。
私はこれまで数多くの経営者と対話してきましたが、業績が停滞している企業ほど、トップが「疑うこと」に強い心理的ブレーキをかけています。たとえば、「社員を信じて任せている」と言いながら、実際は会議で一方的に決定を下す。「うちは風通しがいい」と言いつつ、反対意見を歓迎しない。こうしたズレが積み重なっていくのです。
疑うことを恐れない経営者は、自らに問いを投げかけます。
「この考えは、今の時代にも通用しているか?」
「この判断は、誰のためになっているか?」
その問いがある限り、組織はしなやかに変わり続けることができます。
経営者に必要なのは、「信じ抜く力」と「疑い直す力」の両輪。
疑うことを恐れずに問い直す姿勢こそ、未来を切りひらくリーダーの共通点です。
“当たり前”を守る組織のメカニズム
組織というのは、不思議なもので「変わりたい」と願っていても、同時に「変わりたくない」という力も強く働くものです。これが、“当たり前”を守る組織のメカニズムです。表向きは改革を唱えながら、裏では無意識に現状維持を選んでしまう。そこには、構造的な心理の罠が潜んでいます。
まず、組織は「安心」を求める生き物です。人は未知のものより、たとえ非効率でも“慣れた環境”を好む傾向があります。そのため、経営者が変革を打ち出しても、現場では「どうせまた一時的なブームだろう」「上が言ってるだけ」といった冷めた反応が起きやすい。これは決して悪意ではなく、“安心を守る防衛本能”が働いているのです。
さらに、組織には「同調圧力」という見えない力もあります。新しい提案をした人が浮いてしまったり、空気を乱す存在として扱われたりする。この状況が続くと、社員たちは挑戦することをやめ、“波風を立てない優等生”が増えていきます。結果的に、誰もが「当たり前」を壊さないように気を遣う文化が根づいてしまうのです。
ここで経営者が果たすべき役割は、“壊す側”ではなく“解く側”になること。つまり、無理に壊そうとするのではなく、「なぜこの仕組みが生まれたのか」「今もそれは機能しているのか」と、問いを投げかけていくことです。その対話を通じて、組織の中に新しい“安心の基準”をつくる。これこそが、当たり前を更新する第一歩です。
経営者が変化の旗を掲げるだけでは、組織は動きません。
人の心に寄り添いながら、“当たり前”を解きほぐしていくこと。
それが、真にしなやかな組織をつくるリーダーの力です。
「歯ごたえのある挑戦」が思考を変える
行動変容の第一歩は“違和感”から
経営者が行動を変える最初のきっかけは、決して「完璧な計画」ではありません。むしろ、その前に訪れるのは、胸の奥に生まれる小さな“違和感”です。これが、行動変容の原点です。
「なんだか最近、社員の反応が薄いな」「この会議、前にも同じ話をした気がする」「数字は悪くないけれど、手応えがない」──こうした感覚を見過ごさずに捉えられるかどうかが、経営者の成熟度を分けます。違和感とは、心が発する“気づきのサイン”。理屈ではなく、感性が先に変化を察知しているのです。
私自身、コンサルティング現場で「違和感を感じた瞬間に、必ず立ち止まる」ことを自らに課しています。ある時、長年続けてきた講演内容を準備している最中に、「この話、もう聞き飽きていないか?」という小さな声が聞こえました。勇気を出して構成を一新したところ、聴講者の反応が劇的に変わったのです。違和感を無視していたら、成長のチャンスを逃していたかもしれません。
経営の現場でも同じです。違和感は、組織が変わるチャンスを教えてくれます。
「なんとなく気持ち悪い」「引っかかる」──この小さな感情を“歯ごたえのある課題”に変えることで、初めて行動が動き出すのです。
違和感を大切にするリーダーは、常に自分の感性を信じています。
そしてその感性こそが、組織の未来をひらく羅針盤になるのです。
意識的に“やりづらさ”を選ぶ経営のすすめ
人は誰しも「やりやすい道」を選びたくなるものです。慣れた方法、理解し合える人、成果が見えやすい仕組み──それらは安心をもたらします。しかし、経営者としての成長を考えるなら、ときには“やりづらさ”をあえて選ぶ勇気が必要です。
やりづらさとは、裏を返せば「自分の成長の余白」です。新しい考え方や異なる価値観、反発を感じる意見に触れるとき、そこには摩擦が生まれます。その摩擦こそが、思考を広げ、感性を磨き、リーダーとしての器を大きくしてくれるのです。
たとえば、私自身が経営コンサルタントとして独立した当初、講演のテーマやスタイルを業界の常識から外してみたことがありました。周囲からは「そんなやり方でうまくいくのか?」と懐疑的な声もありましたが、その“やりづらさ”を選んだことで、結果的に「経営写コンサルタント®」という独自のスタイルを確立することができたのです。
経営者にとっての“やりづらさ”とは、未知との出会いの証。現状維持の延長線上に新しい価値は生まれません。だからこそ、あえて手間のかかる道、抵抗を感じる挑戦に踏み出してみる。それが次のステージへの扉を開くカギになります。
“やりやすさ”は安心を与え、“やりづらさ”は成長を与える。
経営とは、そのバランスを取りながら、自らを磨き続ける旅なのです。
“当たり前”を超えて進化する経営者へ
自らの思考を写す「経営写」の視点
経営とは、会社という鏡を通して“自分自身”を見つめる営みです。どれほど優れた戦略を立てても、どんなに立派な理念を掲げても、最終的に企業を動かすのは「経営者の思考そのもの」。だからこそ、私は“経営写(けいえいしゃ)”という視点を大切にしています。
「写す」とは、ただ観察することではありません。ありのままの現実を、歪めずに受け止めることです。つまり、数字や業績の結果だけを見るのではなく、その背景にある“自分の思考のクセ”や“行動のパターン”を写し出すということです。
経営が停滞しているとき、そこには必ず経営者自身の迷いが反映されています。
決断が遅れているのは、どこかで恐れているから。
社員の動きが鈍いのは、経営者自身の情熱が伝わっていないから。
組織の停滞は、リーダーの心の曇りを写している──私はそんな場面を何度も目にしてきました。
だからこそ経営者は、自分を写す「鏡」を持たなければなりません。
それは、数字でも、社員の声でも、あるいは信頼できる相談相手でも構いません。大切なのは、結果を通して“自分の思考”を見直すこと。そこからしか、真の変化は始まりません。
経営写の本質とは、**「会社を通して自分を知り、自分を通して会社を変える」**こと。
この循環が生まれたとき、経営は単なる事業運営から、人生を豊かにする“志事(しごと)”へと昇華します。
経営者が成長を続けるための3つの問い
経営者としての成長には、終わりがありません。
むしろ「もう十分だ」と思った瞬間から、衰退が始まる──これは私が多くの経営者を見てきて確信したことです。変化の激しい時代にあっても、自らを磨き続ける経営者には、共通して“問い”を持ち続ける習慣があります。最後に、私が大切にしている3つの問いをご紹介します。
① 私の「当たり前」は、今も通用しているか?
この問いは、現状への過信を防ぎます。かつての成功や経験が、今の環境でも最善とは限りません。むしろ、“当たり前”の裏側には、時代の変化を見落とす危険が潜んでいます。過去の正解を手放せる人ほど、未来のチャンスをつかめるのです。
② 私の「判断」は、誰のためになっているか?
経営の判断は、常に人の人生に影響します。社員、お客様、家族──自分の決断が“誰の幸せ”に向かっているのかを見失うと、経営は方向を誤ります。「勘定(数字)」だけでなく「感情(心)」にも耳を傾ける。そのバランスが、経営の品格をつくります。
③ 私の「挑戦」は、未来を照らしているか?
経営者が挑戦をやめると、組織は一瞬で停滞します。挑戦とは、結果を出すことよりも、“前に進む意思”そのもの。どれだけ困難でも、自らが先に一歩を踏み出す姿が、周囲に希望を灯します。
これらの問いを繰り返し自分に投げかけることが、経営者としての“筋トレ”です。
「当たり前病」から抜け出す道は、他人が教えてくれるものではなく、自らの内省によって見出すもの。
そしてその先にあるのは、仕事ではなく“志事”としての経営。
自分を磨き続ける経営者こそが、次の時代を導くリーダーなのです。