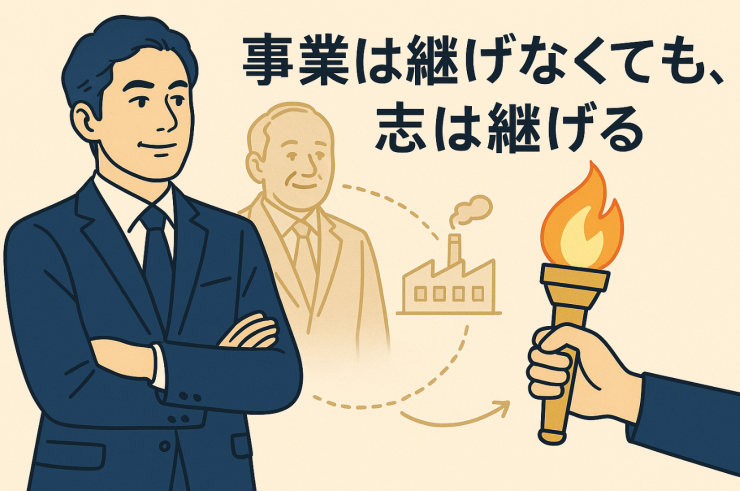「継げなかった」
20代はじめ、中小企業の経営者だった親父が他界した
その後、心にあったのは、コノ言葉だ
自分は社会人やコンサルの道を歩み始めた直後
ただ、経営者の生き様を繋ぎたい心は増していく
【経営者力?】
社長の熱い想いを、社員の心から喜んでの協力を通じて成し遂げ、社会に貢献する力— ふさぽ@経営者 (@future_support) October 28, 2025
「継げなかった」という原体験が教えてくれたもの
父を失い、経営を継げなかった若き日の葛藤
私の父は、地元で中小企業を経営していました。
私が20代のはじめ、社会に出たばかりの頃に、その父が急逝しました。
葬儀のあとの静まり返った事務所に、一人腰を下ろしたときの空気を今でも覚えています。
そこには、机の上に残された帳簿や手紙、社員たちの顔、そして“父の生き様”が、確かに息づいていました。
けれども、私はその経営を継ぐことはできませんでした。
当時の私には、あまりにも力が足りず、覚悟も定まっていなかった。
「なぜ自分が継げなかったのか」――その問いは、長い間、私の胸の中で燻り続けていました。
その葛藤は、単なる「後悔」ではありません。
むしろ、「経営とは何か」「経営者の生き様とは何か」を考え抜くきっかけになったのです。
父の遺した社員たちが見せた“誇り”のような表情。
それは、数字や肩書きではなく、父の人間性そのものへの信頼でした。
継げなかったことの痛みが、やがて私の“原点”になっていきました。
私はその後、経営コンサルタントの道を歩むことになりますが、心の底ではずっと思っていました。
――「父のように、経営者の想いを繋ぐ人間になりたい」と。
失ったものと、心の奥で芽生えた“想いの火種”
父を亡くしたあと、私は“失う”という現実と、真正面から向き合うことになりました。
それは、家族を失う悲しみであると同時に、「経営者としての背中」を失うという、言葉にならない喪失感でもありました。
当時の私は、社会人としての一歩を踏み出したばかり。
父の残した社員たちは、自分よりずっと年上で、経験も豊富でした。
「自分が継げるわけがない」と、心のどこかで言い訳をしていたのかもしれません。
けれど、その“逃げ”の奥には、確かに何かが芽生えていました。
それは、「継げなかった悔しさ」を超えた、“経営者の想い”への敬意でした。
父の姿を通じて感じたのは、経営とは“人の心”を動かす営みだということ。
社員が心から協力し、共に苦楽を分かち合う、その現場の温度でした。
父が遺した事業という「形」は継げなかった。
けれど、父の生き様という「志」は、確かに私の中で火を灯したのです。
この火種こそが、のちに私を“経営者を支える道”へ導いていく――
そう思えば、人生に起こる出来事には、すべて意味があると感じずにはいられません。
「継ぐ」とは何か──血縁ではなく、志縁でつながるもの
「継ぐ」という言葉を聞くと、多くの人は“血”を思い浮かべるのではないでしょうか。
親から子へ、会社を受け継ぐ。
もちろん、それは事業承継の王道であり、尊い形のひとつです。
けれども、年月を重ねるうちに私は気づきました。
“血縁”よりも深い“志縁(しえん)”があるのだということを。
それは、血でつながっていなくても、「想い」でつながる人との縁。
経営者が大切にしてきた理念や姿勢、そして生き方そのものを、次の世代へと繋ごうとする“こころの継承”です。
私はコンサルタントという立場で、多くの経営者の方々と出会ってきました。
その中で見えてきたのは、「事業を継ぐこと」と「志を継ぐこと」は、似て非なるものであるということ。
事業は“形”の継承。
志は“魂”の継承。
どちらか一方が欠けても、組織は長く続きません。
血のつながりではなく、志でつながる。
この“志縁”こそが、これからの時代における真の継承だと、私は確信しています。
なぜなら、志を中心にした関係は、上下や損得を超えた「信頼」で結ばれているからです。
経営を継ぐ者も、継がなかった者も。
大切なのは、“想い”を受け取り、自らの生き方の中で証明すること。
そうして初めて、先人たちの人生が、未来の命へと息づいていくのです。
事業承継と“志承継”の違い
「事業承継」という言葉を耳にするたび、私はその裏にある“もう一つの継承”を思わず考えてしまいます。
それが、“志承継(ししょうけい)”です。
多くの企業では、後継者が経営を引き継ぐ際、株式や資産、ノウハウなどの「目に見えるもの」の継承に注力します。
もちろん、それは事業を存続させるうえで欠かせない要素です。
しかし、経営者として本当に大切なのは、「なぜこの事業を続けているのか」という“想い”の部分――いわば「目に見えない資産」の継承ではないでしょうか。
志承継とは、単なる「後を継ぐ」ことではなく、「心を受け継ぐ」こと。
父の背中から学んだのは、まさにこの“志のバトン”でした。
それは理念や経営方針といった文字情報にとどまらず、
人を信じ、苦しい時こそ前を向き、誰よりも先に汗をかく姿勢――そうした生き方そのものに宿るものです。
私はこれまで、数多くの後継者と向き合ってきました。
その中で感じるのは、事業承継がうまくいかない原因の多くが、“志”の共有不足にあるということ。
数字や体制を整えるだけでは、社員の心はついてこない。
しかし、「この会社をなぜ残したいのか」「誰を幸せにしたいのか」という想いが共有されれば、
自然と周りが動き、未来が動き出す。
志承継こそ、経営の本質。
事業は継げなくても、志を継げる。
それが私自身の経験から導き出した、たったひとつの真理です。
経営者の生き様を支える“見えないバトン”
経営者が引き継ぐのは、会社の看板でも、事業計画でもありません。
本当に受け継がれていくのは、見えないところで流れている“生き様”のバトンです。
父がそうであったように、経営者とは「理念を語る人」ではなく、「理念を体現する人」だと思います。
どれだけ厳しい状況でも、社員や家族の前では笑顔を崩さず、
「大丈夫や、きっと乗り越えられる」と声をかける。
その姿勢が、周りの人の心に深く刻まれていく。
そして、いつの間にかその想いが“見えないバトン”として、誰かの手に渡っていくのです。
私はコンサルタントとして、多くの現場を見てきましたが、
数字では測れないこの“見えない継承”が、実は組織のエネルギー源になっています。
社員がふとした瞬間に「社長ならどうするだろう」と思い出す――その記憶こそが、会社の文化であり、未来を形づくる土台なのです。
バトンは手渡すものではなく、自然に受け取られるもの。
経営者が日々の姿勢で示す生き方こそが、次の世代に受け継がれる最大の遺産なのです。
経営者力とは、想いを形にする“人間力”である
「熱い想い」を“協力の輪”に変えるリーダーシップ
経営者の想いは、どれだけ強くても、独りで完結するものではありません。
想いを実現するには、社員や仲間の“心からの協力”が必要です。
そして、その協力を生み出す源こそが、経営者自身の“人間力”です。
私はこれまで、数多くのリーダーに出会ってきました。
その中で一つ確信しているのは、リーダーは語る人ではなく、伝わる人でなければならないということです。
声を張り上げて理念を語るよりも、日々の行動や表情、姿勢の中に“想い”がにじみ出ている人。
そんなリーダーのもとにこそ、人は自然と集まり、協力の輪が広がっていきます。
たとえば、経営の苦境に立たされた時、社長が自ら汗を流し、社員と同じ目線で動く。
その姿に触れた社員の胸には、言葉では伝えられない“信頼の熱”が宿ります。
この信頼が、組織を支える最大のエネルギーです。
経営者力とは、戦略を練る力よりも、まず「人の心を動かす力」。
その力が、やがて“想い”を“協力の輪”に変えていく。
リーダーとは、周囲を巻き込むのではなく、心を巻き込む人――
それが私の考える、本物のリーダーシップの姿です。
社員が“心から喜んで協力する”組織のつくり方
社員が心から動く組織には、必ず「喜びの循環」があります。
それは、社長が社員を信じ、社員が社長を信じるという“信頼のリズム”です。
このリズムが生まれると、指示がなくても人が動き、困難な局面でも支え合える強いチームになります。
しかし、その循環をつくるのは簡単ではありません。
経営者が「やってほしいこと」を伝える前に、まず「どんな想いでこの仕事をしているか」を語ること。
その背景にある“志”を社員が感じたとき、はじめて仕事が「作業」から「貢献」へと変わります。
私は研修やコンサルティングの現場で、社員の表情が変わる瞬間を何度も見てきました。
それは、社長の本気の想いに触れたときです。
経営者が数字や効率よりも、社員一人ひとりの成長を信じて行動したとき、
その真剣さが伝わり、社員の中に“自分も応えたい”という感情が芽生えます。
つまり、組織を動かすのは「命令」ではなく「共感」。
協力を“求める”のではなく、“引き出す”。
そのためには、経営者自身が一番に「喜びの原点」を忘れないことです。
社員が心から喜んで協力する組織とは、
経営者が“人としての温度”を持ち続ける会社――
そんな温もりこそが、成果よりも長く続く「信頼の資産」になるのです。
経営者の想いを繋ぐ“第三の道”──支援者としての使命
経営者を写し出す「経営写コンサルタント®」という生き方
私が自らを「経営写コンサルタント®」と名乗るようになったのは、単なる肩書きのためではありません。
それは、経営を“写す”ことで、経営者自身の生き方を浮かび上がらせるという使命を込めた言葉です。
私は長年、数多くの経営者と関わってきました。
その中で痛感したのは、経営の本質は「数字」ではなく「人」にあるということ。
決算書や戦略書の裏側には、いつも“その人の想い”と“人生の選択”が刻まれています。
だからこそ、経営者を支援する者として、私はその人の“心の現在地”を見つめることから始めたいと考えています。
経営写コンサルタント®の仕事は、アドバイスをすることではなく、写し出すこと。
つまり、経営者がどんな想いで事業に臨んでいるのか、
どんな場面で迷い、どんな瞬間に喜びを感じているのか――それを鏡のように映し返す。
その対話の中で、経営者は気づきます。
「自分は何のためにこの道を選んだのか」「どこへ向かおうとしているのか」。
この“自己再発見”こそが、経営を再生させる第一歩なのです。
私は、経営者が自らの想いに再び火を灯し、
社員や家族、地域へとその光を広げていく姿を、幾度となく目にしてきました。
その瞬間に立ち会うたびに思います――
経営を支援するとは、人の人生を写す仕事なのだと。
経営を超え、人生に寄り添う支援のあり方
私が経営者を支援するとき、常に意識しているのは「経営」と「人生」を切り離さないことです。
経営の悩みの多くは、実は数字や戦略の問題ではなく、経営者本人の心の状態に根差しています。
その“心の揺らぎ”を放置したままでは、どんな立派な戦略も形になりません。
だからこそ、私は「経営を超えて、人生に寄り添う支援」を大切にしています。
それは、問題を解決すること以上に、“経営者の人生を整える”という姿勢です。
経営者のこころが整えば、判断が澄み、言葉が変わり、社員との関係性にも光が差します。
ある経営者が、私との対話の中でこう言われました。
「水野さん、あなたは経営の話をしているようで、人生の話をしてくれていますね。」
その言葉は、私にとって何よりの褒め言葉でした。
経営とは、人生そのもの。
事業がうまくいくことだけを目標にしては、経営者は長く走り続けられません。
人生の豊かさの上にこそ、事業の繁栄がある。
それが私の信念であり、「経営写コンサルタント®」という生き方の核でもあります。
経営に寄り添うだけでなく、人生に寄り添う。
その覚悟こそが、経営者の“志”を次世代へと繋ぐ最も確かな橋になるのです。
志を継ぐとは、自らの人生で“証明する”こと
経営者の魂をどう未来へ繋ぐか
経営者の魂とは、理念や戦略の奥にある「生き方そのもの」です。
それは紙に書けるものではなく、行動の積み重ねの中ににじみ出るもの。
そして、それを未来へ繋ぐ方法は、教えることでも、押しつけることでもありません。
私はこれまでに、創業者から二代目、三代目へと続く企業を数多く見てきました。
その中で強く感じるのは、「魂の継承」とは“正解を伝えることではなく、想いを託すこと”だということです。
次の世代に必要なのは、過去をそのまま模倣する力ではなく、
先人の想いを自分の言葉で咀嚼し、再び形にする力です。
だから、経営者が残すべきものは「やり方」ではなく「あり方」。
その姿勢が、後継者や社員の心に灯をともします。
たとえ経営の方法が変わっても、想いが通っていれば、その企業は決してぶれません。
経営者の魂を未来へ繋ぐとは、
“誰かが自分を思い出したとき、その背中が勇気を与えるような生き方”をすること。
それが、事業承継を超えた「志承継」の本質だと、私は確信しています。
そしてその生き方は、言葉ではなく、日々の選択によって証明される。
今日どんな一歩を踏み出すかが、未来の誰かを支える礎になるのです。
“生かされた命”に込める想いと、これからの挑戦
私自身、これまでの人生で三度、九死に一生を得る経験をしてきました。
そのたびに強く感じたのは、「生かされている命には使命がある」ということです。
そして、その使命とは“志を次の世代へ繋ぐこと”にほかなりません。
父を継げなかった私が、いま経営者の志を支える仕事に携わっている――
それは、偶然ではなく、必然だったのだと感じます。
あのとき継げなかった事業を、私は“経営者の魂を継ぐ”という形で引き継いでいるのかもしれません。
人生とは、不思議なもので、思い通りにいかない出来事の中にこそ、最も深い意味があります。
失った痛みが、人を磨き、志を育て、他者への優しさに変わる。
だから私は、今もなお、自分の人生を通して「志を証明する旅」を続けています。
これからも、経営者の方々が自らの想いを再発見し、
それを次世代へ繋ぐお手伝いをしていきたい。
経営を超えた“生き方の継承”こそ、私がこの命で果たすべき使命です。
志は、誰かから受け取るものではなく、自らの生き方で繋ぐもの。
そしてそれが、未来の誰かに勇気を与える“見えない火”になる――
私はそう信じています。