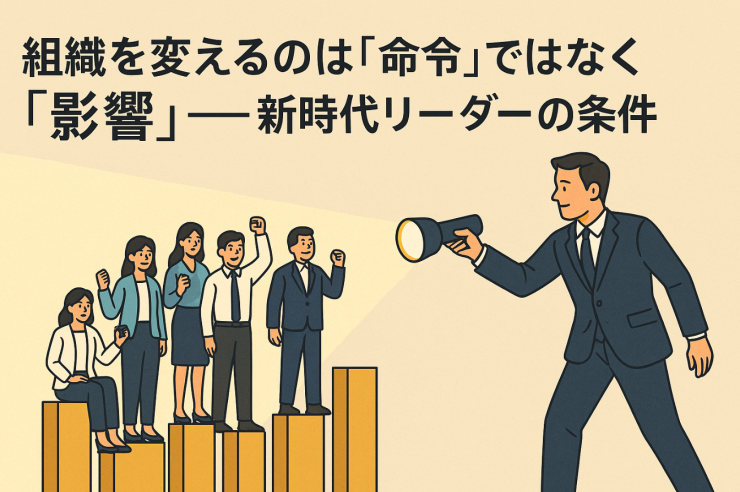リーダーシップって何だろう?
引っ張ること
新任管理職 の頃、長らく想っていた
自分に合っておらず
自分らしさも出しきれず
しかし「押し上げるもあるよね」と
見えはじめより進めれるように
本質は〈影響力〉ではないか
目的目標に向けた対人でのもの
どれが正解かでなく
何が効果的かを探っていく— ふさぽ@経営者 (@future_support) October 22, 2025
リーダーシップの誤解──「引っ張る」がすべてではない
新任管理職の頃に抱いた“リーダーの壁”
新任の管理職として初めて部下を持ったとき、私は「リーダーとは引っ張る存在でなければならない」と信じていました。
チームを先頭で導き、旗を振り、誰よりも頑張って見せる──それが“リーダーシップ”だと。
けれども現実は、理想とはまったく違いました。
いくら声を張り上げても、部下の表情はどこか遠く、会議の場では反応が鈍い。
「なぜついてこないんだ」「何が悪いんだ」と悩むうち、気づけば自分の心がすり減っていく。
結果として、チームの空気も重たくなっていったのです。
そのとき、私は大きな壁にぶつかりました。
“引っ張ること”に集中するあまり、部下の心を置き去りにしていたのです。
自分が正しいと思う方向に皆を動かそうとすればするほど、チームは動かなくなる。
それはまるで、自転車を後ろから無理やり押しているような感覚でした。
今振り返ると、あの経験こそが私のリーダー観を根本から変える出発点でした。
リーダーシップとは「前に出る勇気」だけではなく、「引く勇気」「待つ覚悟」も含めた、
もっと奥深い“人との関係性の学び”なのだと感じたのです。
「自分らしさ」を発揮できないリーダーの共通点
リーダーとして成果を出そうとすればするほど、
私たちは知らず知らずのうちに「理想のリーダー像」に縛られてしまいます。
「もっと強く言わなければ」「厳しく管理しなければ」「チームを引っ張らなければ」──
そう思うあまり、本来の自分らしさを抑え込み、
気づけば“演じるリーダー”になってしまうのです。
しかし、人は“演じる人”には心を開きません。
いくら正しいことを言っても、どこかに違和感を感じ取ります。
なぜなら、言葉よりも先に「姿勢」や「空気感」が伝わるからです。
私自身、かつて「リーダーらしくあろう」と背伸びをしていた時期がありました。
ところが不思議なもので、肩の力を抜いて“素の自分”を出したときの方が、
周囲の反応はむしろ良かったのです。
リーダーに必要なのは“正解の型”ではなく、“自分の軸”です。
他人のリーダー像を真似してもうまくいかない。
けれど、自分の価値観と行動が一致しはじめると、
チームは自然とついてきます。
「自分らしさ」は、リーダーの弱点ではなく最大の武器。
完璧さよりも、誠実さ。
強さよりも、温かさ。
そのバランスの中にこそ、信頼という“影響力”の源があるのです。
リーダーの役割は「押し上げる」ことにある
チームが自走する“支援型リーダーシップ”
かつての私は、「リーダーが引っ張らなければ、組織は止まってしまう」と信じていました。
しかし、現場で多くの経営者や管理職と関わるうちに、
むしろ“押し上げるリーダー”こそが、組織を前進させていると気づかされました。
“押し上げる”とは、部下やチームの力を信じ、その力が発揮できる環境を整えることです。
つまり、指示や命令で動かすのではなく、
「本人が動きたくなる状態」をつくることがリーダーの役割なのです。
たとえば、社員が自ら考え、行動し、成果を上げたとき、
リーダーが一歩引いて「よくやった」と心から讃える。
この一言が、チームに火を灯します。
リーダーの“承認”は、チームの“自走”を生み出す燃料なのです。
支援型リーダーシップの鍵は、「期待」と「信頼」のバランスにあります。
過剰な期待はプレッシャーになり、過剰な信頼は放任になります。
その間にある、“見守りながら支える姿勢”がチームを伸ばすのです。
私はこれを「引く勇気」と呼んでいます。
前に出て引っ張る勇気も必要ですが、
メンバーが成長のチャンスをつかむためには、
リーダーが一歩引いて“舞台を譲る勇気”もまた、大切なのです。
組織の自走とは、リーダーが手放すところから始まります。
そのとき初めて、リーダーは「支配者」ではなく「支援者」になれるのです。
人を育てるとは「任せる」ことでなく「信じる」こと
「人を育てるには、仕事を任せなさい」──
多くの経営書や研修で耳にする言葉ですが、
私はそこにひとつ大切な“前提”が抜けていると感じています。
それは、「任せる前に、信じているかどうか」です。
任せるだけなら、単なる“業務の委譲”です。
しかし、信じて任せることは“人の可能性への投資”です。
この差が、育成の結果を大きく分けます。
信じて任せるとは、「失敗するかもしれない」とわかっていても、
その経験を糧にして立ち上がる力を信頼するということです。
つまり、リーダーが「結果」を支配するのではなく、
「成長のプロセス」を信じて見守る姿勢です。
私が経営写コンサルタントとして関わる中で、
最も変化が大きい組織には、共通して“信頼文化”が根づいています。
そこでは、部下が上司の顔色をうかがうのではなく、
「自分の判断で動ける自由」と「挑戦できる安心」が両立しています。
人は“任される”ことで責任を学び、
“信じられる”ことで力を発揮します。
この二つの要素が重なったとき、
チームは自発的に動き、リーダーの想いを超えて成長していくのです。
リーダーが本気で人を信じるとき、
そこにはコントロールも操作も存在しません。
あるのは、「あなたを信じている」という、
静かで、しかし強烈なメッセージだけです。
本質は〈影響力〉──リーダーシップの新しい定義
命令では動かない時代に求められる関わり方
時代は変わりました。
かつてのように、リーダーが声を上げれば人が動く──そんな時代ではもうありません。
今のチームには、リーダーの「正しさ」よりも、「信頼できるかどうか」が問われています。
“命令”で人を動かす時代から、“影響”で人が動く時代へ。
この変化に、まだ気づいていないリーダーが少なくありません。
命令は「上からの力」、
影響は「内からの力」です。
人は、命令されれば従うことはできます。
しかし、心までは動かせません。
反対に、影響を受けたとき、人は自ら動こうとします。
リーダーに必要なのは、従わせる力ではなく、
“共感を生む力”です。
共感は、相手の心の扉を開き、
「この人と一緒に働きたい」「この人の想いを形にしたい」というエネルギーを引き出します。
では、どうすれば影響力を持てるのか。
それは“言葉”ではなく、“在り方”で示すことです。
たとえば、リーダーが率先して小さな約束を守る、
感情を乱さずに人を受け止める、
ミスを責めずに次の行動を促す。
こうした日々の姿勢こそが、影響力の正体です。
私たちが真に目指すべきは、“動かすリーダー”ではなく、“動きたくなるリーダー”です。
その存在が、命令を超えて人の心に届いたとき、
組織は静かに、しかし確実に変わり始めます。
“影響力”を生む3つの原点(姿勢・言葉・行動)
リーダーの影響力は、カリスマ性や肩書きから生まれるものではありません。
それは、日々の「姿勢」「言葉」「行動」という、ごく基本的な3つの原点から育まれます。
① 姿勢──リーダーの“背中”が語るもの
人は、言葉よりも「姿勢」を見ています。
たとえば、困難な局面でリーダーが焦らず、静かに現状を受け止めている姿は、
それだけでチームに安心感を与えます。
逆に、感情的に動揺するリーダーの背中は、不安を倍増させます。
リーダーの“平常心”は、チームの“平常運転”を支える土台なのです。
② 言葉──伝えるより“響かせる”
リーダーの言葉には重みがあります。
しかし、その重みは声の大きさでも語彙の多さでもなく、
「想いが乗っているか」で決まります。
同じ「ありがとう」でも、そこに心があるかどうかで、相手の受け取り方はまるで違います。
言葉に“温度”を持たせることが、影響力のあるリーダーの特徴です。
③ 行動──小さな一貫性が信頼をつくる
最も影響力を生むのは、“行動の一貫性”です。
言っていることとやっていることが違うリーダーには、人はついてきません。
逆に、たとえ不器用でも、自分の言葉を体現し続ける姿に、人は心を動かされます。
信頼は、派手な結果からではなく、地道な一貫性から生まれるのです。
この3つの原点──姿勢・言葉・行動──は、どれも特別なスキルではありません。
しかし、それらが揃ったときに生まれる“人としての温度”こそが、
リーダーの最大の影響力となるのです。
「正解」ではなく「効果的」を探す思考法
チームや状況に応じて変わる“最適解”
リーダーシップには、「これが正しい」という唯一の答えはありません。
なぜなら、組織も人も、状況も常に変化しているからです。
私が経営者の方々と向き合う中で感じるのは、
“正解”を求めすぎるリーダーほど、行動が止まりやすいということです。
どんなに完璧な計画を立てても、現場には必ず想定外が起こります。
そのときに必要なのは、「正解を当てる力」ではなく、「効果的に動ける柔軟さ」です。
たとえば、ある場面では厳しく方向を示すことが効果的かもしれません。
しかし別の場面では、沈黙して見守る方がチームを動かすこともあります。
大切なのは、“どちらが正しいか”ではなく、“どちらが今、効果的か”という問いです。
リーダーとは、常に変化の中で判断し続ける存在です。
その判断は、数値や理屈だけでは導けません。
メンバーの表情、現場の空気、そして自分自身の直感──
これらを感じ取る感性が、効果的な選択を支えます。
「正解を求める」経営から、「効果を生み出す」経営へ。
この発想の転換こそ、組織の停滞を打ち破る鍵なのです。
そしてそれは、リーダー自身が“変化を恐れない姿勢”を示すことで、初めてチームに伝わります。
経営者が持つべき“問い続ける力”
リーダーにとって、最も危険なのは「もう分かった」と思う瞬間です。
なぜなら、その瞬間から“問い”が止まり、成長が止まるからです。
私が長年経営者の方々と関わってきて痛感するのは、
優れたリーダーほど「答えを出す人」ではなく、「問い続ける人」であるということです。
問いを持つ人は、常に現状を見直し、変化の兆しを捉え、学び続けます。
反対に、答えに固執する人は、変化を拒み、過去の成功体験に縛られてしまうのです。
たとえば、
「このやり方で本当にいいのか?」
「今、メンバーが感じていることは何か?」
「自分の姿勢は信頼を生んでいるだろうか?」
こうした自問自答の習慣こそ、リーダーの器を広げる“内省の力”です。
経営とは、常に未知への挑戦です。
すぐに答えが出る問題よりも、
答えのない問いと向き合う時間にこそ、リーダーの真価が問われます。
そしてもうひとつ、大切なのは“人に問いかける力”です。
「どう思う?」「君ならどうする?」と投げかけることで、
メンバーの中に考える芽が生まれます。
それが組織の知恵となり、共に育つ文化をつくるのです。
リーダーが問い続ける姿は、迷いではなく成熟の証。
答えを急がず、問いを深める。
その姿勢こそが、影響力あるリーダーの共通点なのです。
影響力の源は「生き方」にある──リーダーとしての人間力
人を動かすのは“肩書き”ではなく“信頼”
リーダーという肩書きは、権限を与えるものであっても、信頼を保証するものではありません。
どれほど高い役職に就いていても、信頼がなければ人はついてこない。
一方で、肩書きがなくても信頼される人の言葉には、人を動かす力があります。
信頼とは、日々の小さな積み重ねです。
「約束を守る」「感情を押しつけない」「相手を尊重する」──
そのどれもが、一つひとつの信頼の“貯金”になります。
この積み重ねがやがて、リーダーの影響力という“利息”となって返ってくるのです。
私が関わってきた経営者の中で、最も尊敬する方々に共通しているのは、
“人を変えようとしない”という姿勢です。
彼らは、相手を支配しようとも、操作しようともしません。
ただ、相手を信じ、その可能性を見て、関わり続ける。
この“見守る覚悟”こそが信頼の深さを示しています。
リーダーは、自分の思いどおりに人を動かす存在ではなく、
人が「この人のために」と思って動く存在です。
その原動力は、命令ではなく、尊敬と共感。
つまり、“生き方”そのものが信頼を生み出すのです。
どれだけ言葉を尽くしても、行動が伴わなければ、信頼は育ちません。
反対に、黙っていても“背中で語る人”には、言葉以上の説得力が宿ります。
リーダーの真の影響力とは、語るよりも“在る”ことにあるのです。
組織に希望を灯す“生き様のリーダーシップ”
リーダーの最大の役割は、「希望を灯すこと」だと私は思っています。
経営が厳しいとき、成果が伸び悩むとき、チームが迷いに包まれるとき──
その中でリーダーが発する“希望の言葉”と“姿勢”が、組織全体の光となるのです。
希望とは、現実逃避のポジティブ思考ではありません。
むしろ、現実を直視したうえで「それでも前を向く」という覚悟から生まれます。
リーダーの背中が「大丈夫だ」と語っている限り、
人は安心してもう一歩を踏み出せるのです。
私が多くの企業で目にしてきた成功するリーダーには、ある共通点があります。
それは、“正しいことをする人”ではなく、“誠実であり続ける人”だということです。
人は、完璧なリーダーには憧れますが、誠実なリーダーには心を預けます。
その誠実さが、組織の中に「安心」と「信頼」という文化を根づかせていくのです。
生き様のリーダーシップとは、理論ではなく実践の積み重ねです。
どんな苦境でも諦めず、どんなときも人を大切にする姿勢。
それが周囲に伝わり、やがて“自分もそうありたい”という連鎖を生みます。
この連鎖こそが、組織を持続的に成長させる「影響力の循環」なのです。
そして、その影響は決して一代で終わりません。
誠実に生きるリーダーの姿は、後継者や次の世代の心に刻まれ、
未来の組織文化として受け継がれていく。
それが、“生き様で導くリーダーシップ”の真の力だと私は信じています。