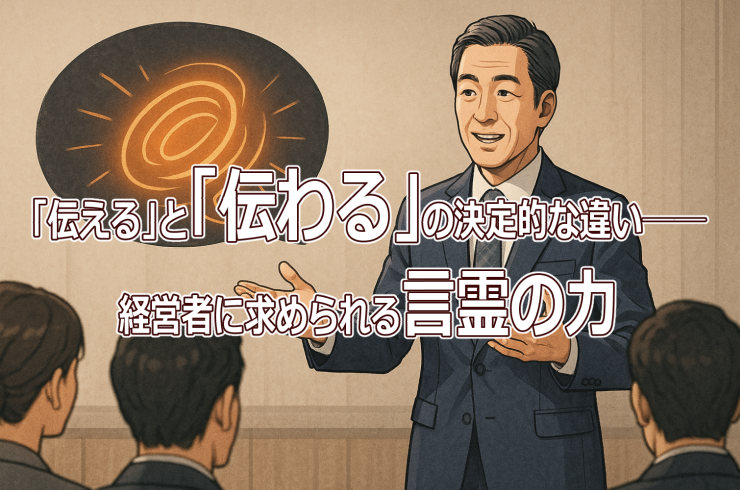【伝わる】
伝えても伝わらない
言っても動かない
と、嘆きたく時はある
が、そんな時こそ、自分のコミュニケーションが確認できるチャンス
①相手が主人公になってるか
②感情に訴えているか?
②相手に合わせた響く言葉か?
③魅了できるイメージか?
〈言葉でなく言霊〉
伝わるを、実践継続したいぃ— ふさぽ@経営者 (@future_support) September 24, 2025
「伝える」と「伝わる」の違いとは?
経営者が陥りやすい“伝わらない”落とし穴
経営者として日々、社員や顧客に向けて想いを伝える場面は数えきれないほどあります。ところが、「伝えたはずなのに動いてくれない」「言葉を尽くしたのに理解されない」と感じることが少なくありません。ここに大きな落とし穴があります。
その多くは、伝えること自体に満足してしまい、相手に届いているかどうかの確認を怠っている点にあります。経営会議で方針を話した、研修で理念を説明した、現場で指示を出した──これらは「伝えた」にすぎません。相手がその言葉を受け取り、心に響き、行動に結びついてこそ「伝わった」と言えるのです。
私自身も経営の現場で、「なぜ理解してもらえないのか」と嘆いた経験があります。振り返ってみると、相手が置かれている状況や感情を考慮せず、自分の論理や都合を優先して話していたのです。つまり、伝え方よりも“自分が話した”という事実に寄りかかっていたのです。
経営者がこの落とし穴から抜け出すためには、まず「伝わらなかったのは相手のせいではなく、自分の伝え方に工夫の余地がある」と受け止めることが出発点です。伝達は一方通行でなく、双方向で育まれるもの。伝える行為を終点にせず、相手の反応を通じて改善を繰り返すことこそが、経営者に求められる姿勢だと痛感しています。
言葉と“言霊”のギャップ
「伝える」と「伝わる」を分ける大きな要素のひとつに、“言葉”と“言霊”の違いがあります。言葉は単なる情報や表現であり、辞書で引けば意味はすぐにわかります。しかし、“言霊”はその言葉に込められた想い、感情、背景までを含んだ生きたエネルギーです。
例えば、同じ「ありがとう」という言葉でも、心からの感謝をこめて発した時と、形式的に口にした時とでは、相手に与える印象はまったく違います。言葉そのものは同じでも、そこに宿る“霊”のような力が相手の心に届くかどうかを左右するのです。
経営者にとって、このギャップを理解することは極めて重要です。どれほど立派な経営理念や方針を語っても、心が伴わなければ社員には響きません。逆に、簡潔な一言でも、そこに真摯な想いが込められていれば、人を動かす力を持ちます。
私自身、講演や研修の場で「先生の話は難しい理論ではなく、自分たちに寄り添ってくれるから響いた」と感想をいただくことがあります。これは、言葉の巧みさ以上に、そこに込めた“想い”が相手に届いた結果だと受け止めています。
言霊を意識するとは、ただ正しい言葉を並べるのではなく、相手を想い、未来を願い、そこに魂を込めて語ることです。経営者の発する言葉に魂が宿るとき、単なる伝達は「伝わる力」へと変わっていきます。
経営者に必要な「相手が主人公」の発想
自分中心の伝達が生む誤解
経営者がメッセージを発するとき、つい「自分の考えを正しく伝えたい」という意識が強くなりがちです。しかし、この姿勢は知らず知らずのうちに“自分中心の伝達”となり、誤解や反発を生む原因になります。
例えば、会議で「こうすれば業績が上がる」と力強く語ったとしても、社員が「自分たちの現場を理解していない」と受け止めれば、言葉は空回りします。経営者が熱を込めて話すほどに、聞き手の心は逆に離れてしまうことさえあるのです。
私もかつて、自分の理想や想いを一方的に語り続け、社員の表情が硬くなるのを感じた経験があります。そのとき気づいたのは、「伝える内容の正しさ」と「受け取る側の気持ち」は必ずしも一致しない、という現実でした。
経営者にとって大切なのは、自分の視点から語るだけではなく、「相手がどのように受け取るか」を想像しながら言葉を選ぶことです。つまり、発信の主体を自分から相手へと切り替える発想の転換が求められるのです。
自分中心の伝達は、相手に“押し付け”と映りやすい。逆に、相手の立場を尊重した言葉は、共感を生み出し、信頼関係を深めます。ここにこそ、伝えるだけでなく“伝わる”ための出発点があるのです。
主人公を相手に変えることで生まれる共感
経営者が語る場面では、自らの信念や理念を熱く伝えたい気持ちは自然なことです。しかし、聞き手にとって「自分ごと」として受け止められなければ、その言葉は心に届きません。ここで大切なのが、“主人公を相手に変える”という視点です。
たとえば、「会社をこう変えたい」という表現を、「皆さんと一緒にこういう未来をつくりたい」と言い換えるだけで、受け手の感じ方は大きく変わります。前者は経営者自身の物語ですが、後者は社員一人ひとりが参加できる物語になります。言葉の焦点を“私”から“あなた”や“私たち”に移すことで、共感の力が一気に広がるのです。
私が講演や研修で意識しているのも、聴衆の方々が「自分のために語られている」と感じられる言葉選びです。ある時、「水野さんの話は、私の心に直接語りかけてくれているように響きました」と感想をいただいたことがありました。これは、単なる情報伝達ではなく、聞き手を主人公とした言霊の力が届いた瞬間だと感じています。
経営者が主人公で語ると、相手は受け身の立場になりやすい。けれども、相手を主人公にした瞬間、その人は行動の主体となります。共感はそこから芽生え、組織を前進させる大きなエネルギーへと変わっていくのです。
感情に響くコミュニケーションの力
論理より感情が人を動かす理由
経営者は日々の意思決定において、数字やデータ、合理的な根拠を大切にします。もちろん経営において論理は欠かせません。しかし、人を動かすのは必ずしも論理ではなく、“感情”であることを忘れてはなりません。
例えば、新しい方針を打ち出す場面で、業績アップのシミュレーションや効率性を説明するだけでは、社員は心から納得しにくいものです。なぜなら、数字は頭で理解できても、心を揺さぶらないからです。逆に、経営者が「この取り組みでお客様がどれほど喜び、社員がどんな笑顔を見せてくれるか」を語ると、社員の心に火がつくことがあります。
私自身も、過去にプレゼンテーションで数字ばかりを並べ立て、聴衆の反応が冷え込んだ経験があります。その後、「数字の裏にある人の想い」を語るように意識を変えたことで、表情や空気が一変しました。つまり、論理は理解を支えるものであり、感情こそが行動を促す原動力だと実感したのです。
経営者が伝えるべきは、単なる計画や目標ではなく、その先にある「人の喜び」「未来の姿」です。数字は感情を支える土台にすぎません。経営者の熱意や願いが乗った言葉こそが、社員を動かし、組織を前進させる推進力となるのです。
感情を揺さぶる具体的な表現方法
感情を動かすためには、単なる事実や理屈の説明にとどまらず、聞き手の心に直接届く表現が必要です。経営者が意識したいのは「具体性」「ストーリー性」「未来像」の三つです。
まず「具体性」。たとえば「お客様に喜んでもらう」と言うよりも、「この商品を手にしたお客様が笑顔で『ありがとう』と言ってくれる姿を思い浮かべてほしい」と伝えた方が、聞き手は場面をイメージできます。イメージできることは感情を動かしやすいのです。
次に「ストーリー性」。人は論理の羅列よりも、物語に心を動かされます。経営者自身の経験や社員の成功事例をストーリーとして語れば、聞き手は「自分もそうなりたい」と自然に感情移入します。私も講演でよく、過去の失敗談や逆境からの学びをお話ししますが、それが聴衆の心に一番響くと感じています。
最後に「未来像」。今の努力がどんな未来につながるのかを具体的に描き出すことで、人は希望を持ち、前に進む力を得ます。「この挑戦を通して、5年後にはどんな会社に成長しているか」を描けるリーダーの言葉は、社員に勇気を与えるのです。
感情を揺さぶる表現とは、難しい言葉や立派な理屈ではなく、「イメージできる言葉」「心に残る物語」「希望ある未来」を伝えることです。それが、経営者の言霊を強くする具体的な手法なのです。
相手に合わせた“響く言葉”を選ぶ技術
一律の言葉が伝わらないワケ
経営者が発するメッセージは、社員全員に向けて発信されることが多いものです。しかし、そこで注意したいのは「一律の言葉」では人に響かないということです。なぜなら、人はそれぞれ立場も状況も価値観も異なるからです。
同じ「頑張ろう」という言葉でも、新入社員には「期待されている」と受け取られても、ベテラン社員には「まだ努力が足りないのか」と響く場合があります。お客様に向けた言葉でも同じです。ある顧客層にはプラスに響く表現が、別の顧客層には冷たく感じられることもあります。
私自身、コンサルティングや講演の場で「この言葉は全員に響くだろう」と思って語ったのに、ある人からは「心に残りました」と言われ、別の人からは「少しきつく感じました」と言われた経験があります。このとき痛感したのは、発信する言葉は“相手の背景によってまったく違う受け止め方をされる”という事実でした。
経営者に求められるのは、全員に同じ言葉を一方的に投げかけることではなく、それぞれの立場や状況に応じて響く表現を工夫することです。人によって受け止め方が異なる前提を持つことで、伝え方の幅は大きく広がります。
一律の言葉は“伝える”だけにとどまり、心に届きません。相手を見極めた言葉こそが、“伝わる”コミュニケーションの第一歩なのです。
相手に響く言葉を見極めるポイント
相手に本当に響く言葉を届けるためには、まず「相手を知る」ことが欠かせません。言葉を選ぶ前に、相手の価値観や置かれている状況を理解しようとする姿勢が大切です。
第一に意識したいのは、相手の立場に立つことです。経営者として「会社全体の成長」を語るのは当然ですが、現場の社員にとっては「今日の仕事をどう乗り越えるか」の方が切実です。そのギャップを埋める言葉を探すことで、相手は「自分ごと」として受け止めやすくなります。
第二に大切なのは、相手の言葉を借りることです。社員や顧客が日常で使っている言葉を取り入れるだけで、ぐっと距離が縮まります。私も研修の場で、参加者が発した言葉を引用しながら話を進めると、「自分たちの声を聞いてくれている」と感じてもらえることが多いのです。
第三に、相手の未来像に寄り添うことです。経営者が語る理想像を一方的に示すのではなく、相手が望んでいる未来と重ね合わせることで、言葉は深く響きます。「あなたが思い描く未来を一緒に実現したい」という姿勢は、何よりの共感を生み出します。
言葉を見極めるとは、辞書から正しい表現を探すことではありません。相手を理解し、その人に寄り添うことで、初めて“響く言葉”が浮かび上がってくるのです。
魅了するイメージと経営者の言霊力
イメージが持つ説得以上の力
人は論理によって納得しますが、イメージによって動かされます。経営者の言葉に説得力があっても、そこに鮮やかなイメージが伴わなければ、聞き手の心は動きません。逆に、シンプルな表現でも具体的なイメージを描けると、説得を超えて人を魅了する力を持ちます。
たとえば「売上を伸ばそう」と言うよりも、「この商品がお客様の生活をどんなふうに変えるのか」を描写する方が、社員は自分の役割を実感しやすくなります。未来の姿を思い描けることで、行動のエネルギーが自然と湧き上がるのです。
私が講演で心がけているのも、数字や理屈だけでなく「情景」を伝えることです。ある経営者の方から「水野さんの話を聞いて、頭で理解しただけでなく、その場面が目の前に浮かんできた」と感想をいただいたことがあります。これは、言葉が単なる情報ではなく、イメージとして届いた瞬間だったのでしょう。
経営者が発する言葉にイメージが伴うと、聞き手は“理解”を超えて“共感”し、“共感”を超えて“行動”へと移ります。説得を超えるイメージの力こそが、リーダーの言霊に宿る大きな魅力なのです。
言霊を磨き続ける経営者の習慣
言霊は一朝一夕で身につくものではありません。経営者が日常の中で磨き続ける習慣こそが、言葉に魂を宿らせる基盤となります。
第一に大切なのは、自らの体験を言葉に変えることです。現場での出来事や経営の葛藤を、日々振り返りながら言葉にしていくと、その言葉には生きた重みが加わります。机上の理論ではなく、経営者自身の歩みから紡がれる言葉だからこそ、聞き手の心に届くのです。
第二に、人の声に耳を傾けること。社員や顧客の声を真摯に聴くことで、相手に寄り添った表現が磨かれていきます。私も講演後の参加者アンケートを一つひとつ丁寧に読み、次に伝える言葉のヒントをいただいています。言霊は自分の中だけで完結するものではなく、人との関わりの中で深まるものです。
第三に、継続的に発信を続けることです。日々のあいさつ、会議での一言、SNSでの発信など、小さな積み重ねが言葉の質を育てます。続けることで、自分自身の思考や価値観も研ぎ澄まされ、言霊の力は自然と磨かれていくのです。
経営者が言霊を意識して習慣を積み上げると、その言葉は人を惹きつけ、組織を動かす大きな力となります。習慣の積み重ねが、リーダーとしての存在感を形づくるのです。
まとめ:伝わるリーダーが組織を動かす
言葉から言霊へシフトするために
経営者が「伝える」から「伝わる」へと変化していくためには、言葉を単なる情報ではなく、言霊として扱う姿勢が求められます。そのための第一歩は、自分の発する言葉に責任と想いを込めることです。軽く投げかけた一言が、社員の行動や会社の未来を左右することもあるのです。
次に大切なのは、言葉の裏側にある“想い”を明確にすることです。経営理念やビジョンを伝える際、「なぜこれを目指すのか」「そこにどんな願いを込めているのか」を語ることで、言葉は単なる説明から魂のこもったメッセージへと変わります。
さらに、行動と一貫させることも欠かせません。言葉と行動が一致しているとき、その言葉には強い説得力と信頼が宿ります。逆に、行動が伴わない言葉は、どれほど立派でも空虚に響いてしまいます。
私自身も、日常の小さな約束を守ることや、社員に語ったことを自ら実践することを意識しています。言葉と行動を一致させることが、結果として「水野さんの言葉には力がある」と受け止めてもらえる理由につながっているのだと実感しています。
言葉を言霊へとシフトすることは、特別な技術ではなく、日々の姿勢の積み重ねです。その積み重ねが経営者の存在感を高め、組織を力強く導いていくのです。
継続的な実践が未来を変える
「伝える」と「伝わる」の違いを理解し、言霊の力を意識したとしても、最初から完璧にできる経営者はいません。大切なのは、日々の実践を続けることです。小さな場面の積み重ねが、やがて大きな変化を生み出します。
社員への朝礼でのひと言、顧客への感謝の挨拶、家族へのねぎらいの言葉──こうした場面で意識して言霊を込めることが、経営者の習慣となり、やがて自然に“伝わる力”として身についていきます。
私自身も、若いころは「どうすれば伝わるのか」と悩み続けました。しかし、伝えるたびに振り返り、少しずつ修正を重ねていくことで、「水野さんの言葉は心に残る」と言っていただけるようになったのです。その過程で学んだのは、「一度でうまくやろうとする必要はない。継続が未来を変える」という真実でした。
経営者の言葉は、組織の文化を形づくり、未来を方向づける力を持っています。だからこそ、日々の実践を惜しまず、繰り返し磨き続けることが重要です。継続する姿勢こそが、経営者自身を成長させ、組織を前進させる原動力になるのです。