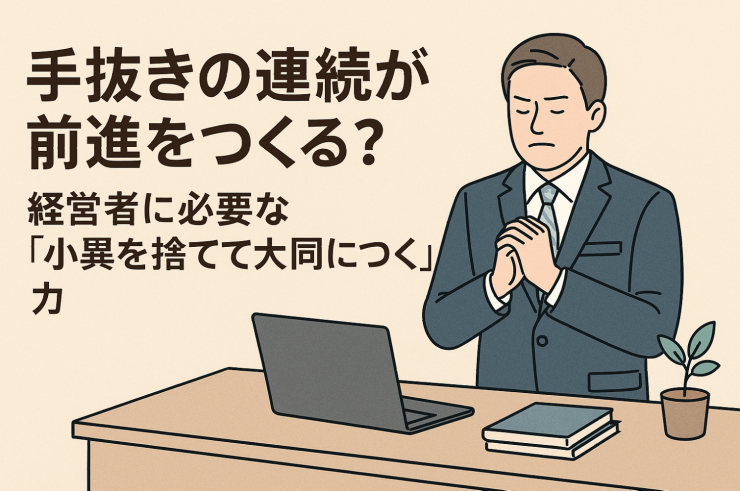【整える】
メンタルヘルスや自己肯定感、完璧主義を手放す等々、イロイロな言葉を耳にする
最近出会った言葉では
いいかげん、ではなく良い加減
を超えて
手抜きの連続で続ける、というもの
〈小異を捨てて大同につく〉
これがあれば継続ができ、結果
前進や成果が生まれてくるのかも
あなたはどう?— ふさぽ@経営者 (@future_support) September 23, 2025
「整える」という発想が経営者にもたらすもの
メンタルヘルスや自己肯定感との関係
経営者にとって「整える」という言葉は、単なる気分転換や健康法ではありません。むしろ、日々の経営判断や組織運営を安定させるための基盤と言えます。メンタルヘルスが乱れると、冷静な判断力が鈍り、ちょっとした問題が大きな不安となりやすい。自己肯定感が低下すれば「自分はダメだ」との思い込みから、必要以上に完璧を求めてしまう悪循環に陥ります。
そこで大切なのが「整える」という習慣です。呼吸を整え、生活のリズムを整え、時には感情を整える。小さな積み重ねが、自己肯定感を支え、経営者としての安定感をつくっていきます。完璧でなくてもよい、自分なりの“良い加減”を持つことこそ、心の余白を生み出す第一歩なのです。
私自身、講演の場でよくお伝えするのは「心が揺れるのは自然なこと。しかし整える習慣があれば立ち直りは早い」ということです。揺れをなくすのではなく、戻る力を育てる。それが経営者の自己肯定感を高め、事業を支える力になるのではないでしょうか。
完璧主義を手放すことの意味
経営者にとって「完璧にやり遂げる」という姿勢は、一見すると頼もしいものに映ります。しかし、その完璧主義が行き過ぎるとどうなるでしょうか。部下に過度な要求をしたり、ほんの小さな失敗を許せなくなったり。結果として組織全体が疲弊し、成長の芽を自ら摘んでしまうことがあるのです。
「整える」という考え方は、完璧を求めるのではなく“ちょうど良い状態”を保つことに意味があります。小さな手抜きや調整を認めることで、継続できる余力が生まれる。経営者にとっては、この「余白」が長期的な成果をつくるエネルギー源になります。
私自身も若い頃は「経営者は強く、間違いなく判断すべきだ」と思い込んでいました。ところが実際には、不完全さを受け入れた時の方が、組織は柔軟に動き出し、メンバーも主体的に考えるようになる。完璧を手放すことは、弱さではなく、むしろ経営の持続性を高める“強さ”だと気づかされました。
「いいかげん」ではなく「良い加減」を超えて
継続を支える“手抜き”という逆説的アプローチ
「手抜き」という言葉には、一般的にネガティブな響きがあります。しかし、ここでいう手抜きは“ラクをする”ことではなく、“力を抜く”という意味合いに近いのです。経営者の日常は決断と責任の連続であり、常に全力投球では長く続きません。むしろ、意識的に“手を抜く”部分をつくることで、長期的な継続が可能になるのです。
例えば、会議の議事録を自分で一字一句まとめるのではなく、要点をチームに任せる。あるいは、日々の細かい数字をすべて把握するのではなく、重要な指標だけを確認する。これらは決して怠慢ではなく、エネルギーの使いどころを整える工夫です。
私自身、トレイルランニングや登山をする際に痛感するのですが、力を抜くポイントを知らないと長い距離は走れません。休むべき時に休み、歩幅を小さく調整しながら進むからこそ、ゴールに辿り着ける。経営における“手抜き”も同じで、余力を残すことで挑戦を続けられるのです。
経営者にとって本当の危険は、頑張りすぎて続けられなくなること。だからこそ「手抜きの連続」が、むしろ成果を積み重ねる秘訣になるのではないでしょうか。
小さな妥協が生み出す大きな成果
経営の現場では、「一切妥協しない」という姿勢が美徳のように語られることがあります。しかし、すべてにおいて完璧を追い求めれば、現場は硬直し、スピード感を失いかねません。むしろ、日常の小さな妥協を許すことが、結果的に大きな前進を生み出すことがあるのです。
たとえば、社内の資料フォーマットを完璧に統一することにこだわりすぎると、社員の負担が増え、肝心のアイデアや提案が出にくくなる。そこで「最低限ここだけ整っていれば良い」と線を引けば、スピード感を保ちながら本質に集中できます。
私が講演でよく伝えるのは、「小異を捨てて大同につく」という考え方です。細部へのこだわりを緩め、組織の大きな方向性を一致させること。これが、経営を持続的に成長させる力となります。
小さな妥協は、弱さではありません。それは全体を前進させるための戦略的選択です。結果として、経営者も社員もエネルギーを本当に必要なところに注ぐことができ、チームとしての成果が大きく育っていくのです。
〈小異を捨てて大同につく〉が教える経営の知恵
個々のこだわりよりも全体最適を重視する姿勢
経営の場では、社員一人ひとりが「自分のやり方」にこだわりを持つことは決して悪いことではありません。むしろ専門性を高めるうえで必要な姿勢とも言えます。しかし、そのこだわりが組織全体の流れを阻害してしまうと、本来得られるはずの成果が小さくなってしまうのです。
「全体最適」とは、個人や部署の満足を一段脇に置き、会社全体の利益や方向性を優先する考え方です。経営者がリーダーシップを発揮するポイントは、まさにここにあります。ある人の100点を追い求めるよりも、組織全体が70点で揃う方が前進は早い。部分的な正解を積み重ねるより、全体の調和を意識することで成長の速度は加速していきます。
私自身、これまでのコンサルティングの場で何度も体験しました。経営者が「自分の会社の強みはここだから」と一点突破を狙いすぎると、他の領域とのバランスが崩れて持続性を失うケースがあります。逆に、小異を捨てて全体像を整えた時、想像以上に組織力が増し、成果が一気に広がっていくのです。
全体最適を選ぶ姿勢は、ときに痛みを伴います。しかし、その選択こそが組織を次のステージに押し上げる力になるのです。
チーム経営に活きる“整える力”
チームで経営を進めるとき、最も重要なのは「全員が同じ方向を向けるかどうか」です。ビジョンや目標がバラバラであれば、どんなに優秀なメンバーを揃えても力は分散してしまいます。そこで求められるのが、“整える力”です。
整えるとは、単に規律を正すことではなく、価値観や優先順位をそろえていくことです。経営者がまず自分の心を整え、次に組織全体の空気を整えていく。その積み重ねが「共に働く意味」を育みます。
実際に、私が関わったある中小企業では、各部署が自分の成果だけを追いかけていたため、社内は常にギスギスしていました。そこで「会社として最も大切にすること」を経営者が明確にし、会議や日常の会話で繰り返し共有しました。すると徐々に部署間の壁が薄れ、互いに助け合う文化が芽生え、売上だけでなく社員の笑顔も増えていったのです。
チーム経営において、“整える力”は摩擦を減らし、協働を加速させます。これは特別なリーダーだけが持つ資質ではなく、日々の習慣の積み重ねで誰もが磨ける力なのです。
成果を生み続けるリーダーの整え方
継続の仕組み化と環境づくり
経営において大切なのは「一時的な成果」よりも「続けられる仕組み」を持つことです。どれほど立派な戦略でも、現場で続けられなければ意味がありません。だからこそ、経営者が意識すべきは仕組み化と環境づくりです。
仕組み化とは、成果を出す行動を“習慣”に落とし込むことです。例えば、毎週の定例会で数値を確認するだけでなく、「次の一手」を必ず話すようにルール化する。あるいは、経営理念を毎朝の朝礼で共有する。こうした仕組みが、日々の行動を自然と前進させるのです。
同時に欠かせないのが環境づくりです。人は環境に大きく影響されます。例えば、経営者が「挑戦を歓迎する雰囲気」を整えると、社員は新しい提案を出しやすくなります。逆に、失敗を恐れる空気が蔓延すれば、どんな優秀な人材も力を出し切れません。
私自身、講演や研修で繰り返し伝えるのは「人が育つのは、環境が育つから」ということです。継続の仕組みと環境がそろえば、経営は自ずと前進し、成果は積み重なっていくのです。
自己肯定感を高める「小さな成功体験」
経営者にとって自己肯定感は、判断力やリーダーシップの源泉です。しかし、日々のプレッシャーや結果への不安から、自信を失いやすい立場でもあります。そこで鍵となるのが「小さな成功体験」を積み重ねることです。
大きな成果は一朝一夕には得られませんが、小さな達成を認め、喜ぶことは誰にでもできます。例えば、予定通りに会議が進んだ、社員が自主的に意見を出した、新しい顧客との面談で前向きな反応を得た──こうした日常の小さな一歩を「成果」として意識するのです。
この積み重ねが「自分はやれる」という感覚を育み、自己肯定感を高めます。そして経営者が前向きなエネルギーを発すると、社員や組織にもその波及効果が広がっていきます。
私自身、講演の場で「小さな成功を見逃さないことが、大きな飛躍の布石になる」とよくお伝えします。経営者の自己肯定感は、組織全体の肯定感を高める起点です。小さな成功体験を認める習慣が、未来の大きな成果を支えていくのです。
まとめ:手抜きの継続が前進をつくる理由
継続こそ経営の最大の資産
経営において、最も大きな資産は「継続」だと私は考えています。利益や人材、商品やサービスはもちろん大切ですが、それらを支える土台は「続ける力」にあります。続けることができれば改善や工夫が積み重なり、やがて大きな成果へと結びついていくのです。
しかし、継続には必ず波があります。好調な時期には順調に進められても、不調に陥った途端に歩みが止まるケースは少なくありません。だからこそ、調子が悪い時でも“続けられる仕組み”を持つことが重要です。それが「整える」という発想に直結します。
私が出会ってきた経営者の中で長期に成果を出している方々は、例外なく「続ける仕組み」を持っていました。毎日の習慣、定期的な振り返り、数字に基づく確認など。完璧でなくても構わない、続けていること自体が価値となり、信頼となっていくのです。
経営の世界では、短期的な勝負よりも、長期にわたる継続こそが真の競争力となります。継続は地味ですが、最大の資産。それを支えるのが「整える力」なのです。
「整える」習慣が未来をひらく
経営は常に変化の中にあります。景気の波、顧客ニーズの変化、予期せぬトラブル──こうした外部環境に振り回されずに前進し続けるために必要なのが「整える」習慣です。
整えるとは、一度きりの特別な行動ではなく、毎日の小さな積み重ねです。心を整える、場を整える、人間関係を整える。そうした日常の習慣が、いざという時に経営者を支え、未来を切りひらく力となります。
私自身、これまで多くの経営者と関わってきて感じるのは、「大きな成果を上げる人ほど、小さな整え方を怠らない」ということです。雑然とした環境のまま突き進むのではなく、一度立ち止まって整理をし、心を調える。その姿勢が、長期的に信頼されるリーダー像をつくり出します。
経営における未来は、遠いどこかにあるのではなく、日々の整える習慣から生まれます。今日の小さな整え方が、明日の成果、そして企業の未来を築いていくのです。