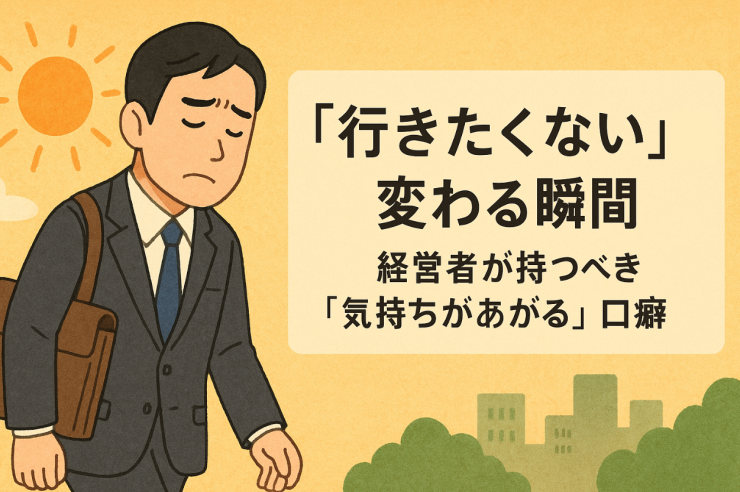ホント?
”まだ続く暑さ”の中
「やる気がでない」との声が
はたして気候や環境のせいか
30代、通っていた場所に向かう道で
「今日は気分が乗らない」と感じた
何回も『行きたくない』と口にした
感情が出尽くしスッキリ
その後、行く意味があふれ出る
あげる
でなく
気持ちが『あがる』口癖を、問いたい— ふさぽ@経営者 (@future_support) September 10, 2025
「行きたくない」と感じるのはなぜか?
暑さや環境の影響による気分の低下
夏の厳しい暑さや湿度の高さは、心身に大きな負担を与えます。体が重く感じられ、自然と「今日はやる気が出ない」と言葉が口から出てしまう。これは生理的な反応でもあり、誰もが経験することです。特に経営者は日々多くの判断や決断を迫られる立場にあり、気候や環境の影響をそのまま仕事に持ち込むと、集中力や判断力の低下に直結してしまいます。
私自身も若い頃、炎天下の営業や打ち合わせに出かける道すがら、「今日は気分が乗らない」とつい弱音を吐いたことがありました。しかし不思議なもので、その感情を意識的に切り替えないと、一日中その気分に引きずられてしまうのです。
だからこそ経営者には、暑さや環境の影響をただ受け入れるのではなく、「ここからどう整えるか」と問う姿勢が求められます。体調を調える工夫も大切ですが、同時に“口癖”が気持ちの方向性を決める大きな鍵となるのです。
感情が停滞する時の経営者の心理
経営者であっても、人間ですから気分が沈むことは当然あります。日々の業務の重圧、周囲からの期待、そして先の見えない不安。こうした要因が積み重なると、「今日はどうしても前に進みたくない」と感じる瞬間が訪れます。
私も30代の頃、ある研修先へ向かう道すがら、何度も「行きたくない」と心の中でつぶやいた経験があります。まるで足取りが重くなり、胸の中にモヤモヤが溜まっていくような感覚でした。経営者にとって、このような停滞感は決して珍しいものではありません。
しかし興味深いのは、その「停滞の感情」を否定せず、素直に口に出したり認めたりすると、かえって心がスッと軽くなることです。感情が出尽くすと、逆に「なぜ自分はそこへ向かうのか」という意味や目的が見えてくる。この切り替えの瞬間こそが、経営者にとって重要な心理のプロセスなのです。
停滞を完全に避けることはできませんが、その時にどんな言葉を選ぶかで、その後の行動と成果が大きく変わっていきます。
口癖が気持ちを左右するメカニズム
ネガティブな言葉が行動を止める理由
「行きたくない」「やる気が出ない」といった口癖は、一見ただの気持ちの表現に見えます。しかし実際には、自分自身の行動にブレーキをかける強い暗示となります。言葉は思考を形づくり、思考は行動を左右するからです。
経営者は日々、大小さまざまな決断を迫られます。そのとき、無意識にネガティブな言葉を口にしていると、挑戦よりも回避を選びやすくなり、結果として組織のスピードや成長のチャンスを失ってしまうのです。
私も経験がありますが、弱音の口癖を繰り返していると、気持ちだけでなく姿勢まで下向きになり、周囲に伝わる空気も重くなります。特にリーダーの言葉は社員に影響を与えるため、組織全体の士気を下げる要因となりかねません。
つまりネガティブな口癖は、本人の行動を止めるだけでなく、周りの可能性までも閉ざしてしまうのです。だからこそ、経営者ほど「どんな言葉を選ぶか」が重要になってきます。
感情を吐き出すことで心が軽くなる効果
「行きたくない」「気分が乗らない」といった言葉は、決して悪者ではありません。むしろ、心の中に溜め込んでしまうより、外に出すことで気持ちが整理されることがあります。人は感情を言葉にすることで、初めて自分の状態を客観的に捉えられるようになるのです。
私自身、ある時「もう嫌だ」と繰り返し口にした後、ふっと肩の力が抜けて楽になった経験があります。その瞬間、なぜ自分がその場に向かう必要があるのか、原点や意味が見えてきたのです。経営者にとっても同じで、感情を無理に押し殺すよりも、一度外に出してしまった方が次の一歩を踏み出しやすくなります。
大切なのは、吐き出したまま終わらせないことです。「行きたくない」と言った後に、「でも自分が行くことで誰かの役に立てる」といった前向きな言葉に切り替える。この“感情の浄化から前進への転換”こそ、口癖を経営に活かす上での大切なポイントです。
“気持ちがあがる”口癖の実践例
「今日はこんなチャンスがある」と言い換える
ネガティブな口癖をそのまま放置すると、気分だけでなく行動まで引きずられてしまいます。そこで効果的なのが、「行きたくない」を「今日はこんなチャンスがある」に言い換えることです。
例えば、「暑いし面倒だ」と思った瞬間に、「今日は新しい出会いがあるかもしれない」「この場で学べることがある」と視点を変えてみる。言葉を置き換えるだけで、心が少しずつ前を向きはじめます。
私自身、訪問先に向かう途中で「気が重いな」と感じた際、あえて「ここで自分にしかできない価値を届けられる」と言い直したことで、足取りが軽くなった経験があります。経営者にとって、自分を鼓舞する言葉は一種のセルフマネジメントであり、周囲に伝わる空気を変える力にもなります。
言葉は現実をつくる力を持っています。「行きたくない」を「チャンスがある」に変換することで、行動の質も結果も変わっていくのです。
前向きなセルフトークで集中力を引き出す
経営者にとって日々の判断や行動には、集中力の維持が欠かせません。その集中力を支えるのが「セルフトーク」、つまり自分自身への語りかけです。
「どうせうまくいかない」とつぶやけば、心は不安に傾き、思考は散漫になっていきます。逆に「今日できることを一つずつやろう」「自分なら乗り越えられる」と声に出せば、不思議と気持ちが整い、目の前のことに集中できるようになります。
私が研修やコンサルティングで出会った経営者の中にも、口癖を工夫して成果を上げている方が多くいます。「よし、やってみよう」「まず一歩進もう」といった短い言葉を繰り返すだけで、気持ちの切り替えが早くなるのです。
セルフトークは、特別な技術や大きな時間を必要としません。日常の小さな場面で前向きな言葉を選ぶことで、集中力を高め、自らの行動を後押しできる。それが経営者にとって大きな武器になるのです。
経営者に求められるセルフマネジメント力
言葉を変えることで意思決定が変わる
経営者にとって日々の意思決定は、会社の方向性を左右する大きな仕事です。その判断の質を高めるうえで、実は「どんな言葉を自分に投げかけているか」が大きく影響します。
「どうせ無理だ」と言えば、その時点で選択肢を狭め、挑戦の芽を摘んでしまいます。反対に「できる方法は何か」と言葉を変えることで、可能性に目を向ける思考が働き、具体的な行動策を導き出せるようになります。
私もかつて、難しい案件に直面したとき「やめておこう」と弱気になったことがあります。しかし「まずは一歩試してみよう」と言い換えた途端、状況を打開するアイデアが浮かび、最終的には成果につながった経験があります。
つまり、言葉は単なる気分の問題ではなく、経営判断そのものを左右する要因です。自分にかける言葉を変えることが、組織の未来を変える意思決定につながっていくのです。
組織に伝わるリーダーの口癖の影響
経営者やリーダーの口癖は、自分だけでなく組織全体に広がっていく力を持っています。トップが日常的に「疲れた」「無理だ」といった言葉を口にしていれば、社員も無意識に同じ空気を吸い込み、挑戦する前からあきらめムードが漂ってしまいます。
逆に「やってみよう」「一緒に考えよう」といった前向きな言葉を口癖にしているリーダーのもとでは、社員の表情や行動が明るくなり、挑戦を後押しする雰囲気が自然と生まれます。これは単なる精神論ではなく、言葉が感情を動かし、感情が行動を変え、行動が結果をつくるというプロセスそのものです。
私自身も、チームメンバーに向けて「ありがとう」「助かるよ」と口にするよう意識したことで、場の雰囲気が柔らかくなり、相談や提案が以前より活発になった経験があります。リーダーの口癖は組織文化を形づくる種のようなもの。どんな種をまくかによって、組織の未来は大きく変わるのです。
まとめ:未来を切り拓く言葉の習慣
気持ちを“あげる”口癖がもたらす可能性
「行きたくない」と口にすれば足取りは重くなりますが、「よし、やってみよう」と声に出せば不思議と背筋が伸びる。気持ちを“あげる”口癖には、未来を開く力があります。
経営者が日常的に前向きな言葉を選ぶことで、自分自身のモチベーションが整うだけでなく、社員や取引先にも良い影響を与えます。小さな口癖の積み重ねが、やがて大きな信頼感や挑戦の文化をつくりあげるのです。
私がご一緒してきた経営者の中には、「ワクワクするね」「面白い!」を口癖にしている方がいます。その方の会社は常に新しい発想が生まれ、社員の挑戦意欲も高い。まさに口癖が企業文化を育てている好例でした。
気持ちを“あげる”言葉は、経営の厳しい局面でも力を発揮します。困難に直面したときこそ、どんな言葉を口にするかが試される。前向きな口癖は、未来への灯りをともすスイッチなのです。
経営者人生に活かす言霊の力
日本には古くから「言霊(ことだま)」という考え方があります。言葉には魂が宿り、口にしたことが現実を動かす力を持つというものです。経営者の口癖はまさにその言霊であり、人生や事業の流れを左右する重要な要素だといえるでしょう。
「できない」と言えば、その瞬間に道は閉ざされます。しかし「できる方法を探そう」と言えば、視野が広がり、チャンスが見えてきます。言葉は未来の方向性を示す羅針盤のようなものなのです。
私自身、九死に一生を得た経験を通じて、「生かされた命をどう活かすか」という言葉を自らに問い続けてきました。その言葉があったからこそ、今も経営者の方々に寄り添う活動を続けられているのだと実感しています。
経営者の人生は決断と挑戦の連続です。その歩みの中で、どんな言葉を選び、どんな口癖を身につけるか。その積み重ねが、経営者自身の未来を形づくり、組織や社会にも大きな影響を与えていくのです。