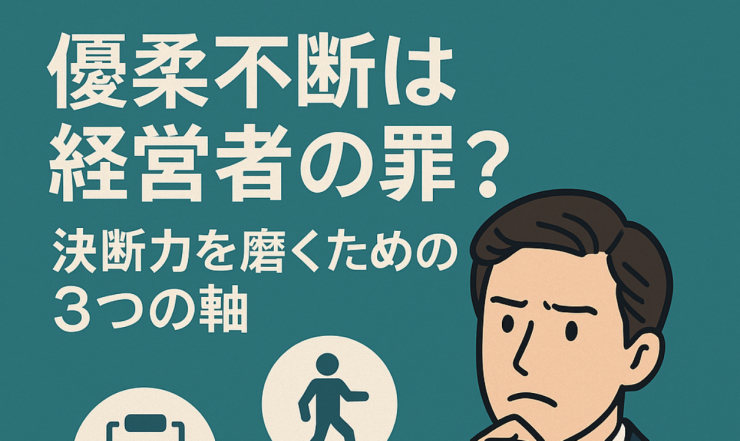【判断】
経営者としての日常は決めること
「優柔不断は経営者の罪悪」と、先輩の方々からも、導かれた
そう学びブレてはいけないと想えど〈決定〉に悩み苦しむ時もあった
しかし、正解はないと捉え
①生き様 働き様を軸に
②判断基準の明確化
③《決心》で挑む
ことで、的確な判断が進むようになれた— ふさぽ@経営者 (@future_support) September 4, 2025
経営者にとって「優柔不断」が罪とされる理由
決断力が企業の命運を左右する
経営者の仕事は、日々の「決断」の積み重ねです。たとえ小さな判断であっても、それが積もり重なった先に企業の未来が形づくられていきます。とりわけ中小企業においては、トップの一声がそのまま現場に直結するため、決断の速さと正確さが企業の命運を分けることも少なくありません。
私自身もこれまでに、躊躇して好機を逃した経験があります。逆に、多少の不安があっても「やる」と決めて踏み出した結果、取引先や社員の信頼を得て、新たな成長のきっかけを掴んだこともありました。決断が正解かどうかは、結果が出て初めて分かるもの。しかし、決めなければ何も始まらない。経営者にとって判断力は、企業を動かすエンジンそのものだと感じています。
優柔不断がもたらす組織への悪影響
経営者が決断を先送りにすると、その迷いは組織全体に伝染します。社員から見れば「社長が迷っている=会社の方向性が不透明」という印象を与え、不安や不信感につながります。その結果、現場は判断を避け、責任を取りたくない空気が広がり、挑戦する力が失われてしまいます。
私が関わった企業でも、トップが意思決定を先延ばしにしたことで、社員が動けず、競合に先を越された事例がありました。逆に、社長が明確に「この道で行く」と示すと、社員も安心して力を発揮できるものです。もちろん決断にはリスクが伴いますが、優柔不断はリスク以上に「組織の士気低下」という目に見えにくい損失を生みます。
経営者の迷いはそのまま会社の迷い。だからこそ、判断の姿勢を社員に示すことが、経営者に求められる最初の責任だと感じています。
正解のない時代に必要な経営判断のスタンス
100点を求めず最適解を選ぶ思考法
経営判断に「正解」はありません。なぜなら、未来は誰にも読めないからです。経営者が判断に迷うとき、多くの場合「もっと完璧な答えがあるのでは」と100点を探そうとしているのです。しかし、その迷いこそが行動を止め、結果的に機会を失う原因となります。
私が学んだのは、「60点でも実行に移す勇気」の大切さです。残りの40点は、実行しながら修正して積み重ねればよい。経営は試験問題ではなく、常に変化し続ける現場です。行動のスピードと柔軟性が、結果として最適解を導いてくれるのです。
要は「最初から正しいか」ではなく、「実行後に正しくしていけるか」が勝負。完璧を目指すよりも、現時点での最善を選び、挑戦する。その繰り返しが、経営者としての判断力を磨くことにつながります。
判断に迷った時の心構え
経営者が判断に迷うのは、当然のことです。なぜなら、影響を受けるのは取引先や社員、さらには家族まで広がるからです。私自身も何度も悩み、夜眠れないほど思い詰めた経験があります。しかし大切なのは「迷う自分を否定しない」ことでした。
迷うということは、それだけ責任を重く受け止めている証拠でもあります。だからこそ、行き詰まったときは「原点」に立ち返ることが心を落ち着ける一歩になります。自分の生き様や働き様に照らし合わせて、この決断が自分らしいかどうかを問うのです。
また、判断に迷ったときは「期限を切る」ことも重要です。いつまでも悩み続けるのではなく、「ここまで考えたら決める」と線を引く。そうすることで、不安に流されず、前に進む力を持てるようになります。
迷いは弱さではなく、未来をより良くしたいという想いの裏返し。経営者にとっては、迷いを受け止めつつも、最終的に一歩を踏み出す覚悟が大切なのです。
決断力を磨くための3つの軸とは?
生き様・働き様を軸に据える
経営者の判断には、数字や戦略だけでなく「自分はどう生きたいのか」「どんな働き様を貫きたいのか」という人生観が深く関わっています。なぜなら、経営判断とは単なるビジネス上の選択ではなく、自分自身のあり方を社会に問う行為だからです。
私自身、迷ったときには「この決断は、自分の生き様に誇れるものか?」と問い直してきました。利益を優先するあまり心に反する選択をすれば、たとえ短期的に成功しても、どこかで自分を裏切ることになります。一方で、自分の働き様に照らして納得した決断は、たとえ失敗しても成長の糧となり、次の挑戦につながります。
経営者が「生き様・働き様」を軸に持つことで、判断はぶれにくくなり、周囲からも信頼を得られるようになります。会社にとっても社員にとっても、揺るがない軸を持つリーダーは安心感を与える存在となるのです。
判断基準を明確にする
経営者にとって重要なのは、「何をもって判断するのか」という基準を明確に持つことです。基準が曖昧だと、その場の雰囲気や感情に流されやすくなり、結果として判断に一貫性がなくなります。逆に、判断基準がはっきりしていれば、どんな状況でも迷いが減り、決断のスピードと質が高まります。
私が大切にしているのは、「長期的な視点で企業と人を豊かにするかどうか」という基準です。目先の利益だけを追えば、短期的にはプラスでも、信頼を失うことにつながります。数字だけでなく、人間関係や社員の成長など、複合的な視点で基準を置くことで、より健全な経営判断ができるようになりました。
また、基準を言葉として明文化しておくことも効果的です。経営理念やビジョンの形で整理すれば、経営者自身が迷いにくくなるだけでなく、社員も同じ基準で動けるようになります。判断の軸を共有することが、組織全体の一体感にもつながるのです。
《決心》で挑む
最後に大切なのは「決心」です。判断基準をいくら整えても、最終的に「やる」と腹を括らなければ前には進めません。経営者にとって決心とは、結果がどう転んでも自ら責任を引き受ける覚悟を示すことです。
私も若い頃は「もっと情報を集めてから」と先送りしてしまうことがありました。しかし、いくら考えても未来は誰にも予測できません。ある時、尊敬する先輩経営者から「決めること自体が力になるんや」と教わり、迷うよりも一歩踏み出す勇気を優先するようになりました。
決心が固まると、不思議と周囲も安心し、動きがスムーズになります。社員はリーダーの覚悟を敏感に感じ取りますから、決心を示すことで信頼と共感が生まれるのです。経営者が挑む姿を見せることこそが、組織を前進させる最大のエネルギーになるのではないでしょうか。
判断力を実践に活かす具体的な方法
日常の小さな選択から訓練する
大きな経営判断を下す力は、いきなり身につくものではありません。むしろ、日常の小さな選択を意識して積み重ねることで、自然と決断力は鍛えられていきます。たとえば「今日の会議は何を優先するか」「どの案件から着手するか」といった一見些細な選択でも、自分の基準を持って即断する習慣が大切です。
私自身も、毎日の生活の中で「迷ったらやる」「期限を決めて決める」とルールを設けています。こうした小さなトレーニングを繰り返すことで、いざという時に迷いすぎず、大きな判断も腹を括れるようになりました。
経営者は常に「決める人」です。そのための筋力をつけるには、日常をトレーニングの場にすることが一番の近道だと実感しています。小さな選択の積み重ねが、やがて企業の命運を左右する大きな決断力へとつながっていくのです。
数字と感情の両面でバランスを取る
経営判断において、数字は欠かせない根拠です。売上や利益、キャッシュフローといった指標を抜きにしては、持続的な経営は成り立ちません。しかし一方で、数字だけに頼った判断は、人の気持ちを置き去りにしてしまいます。社員や顧客の感情を軽視すると、信頼を失い、長期的には数字さえも悪化してしまうのです。
私が意識しているのは、「右手に経営理念、左手に決算書」という考え方です。つまり、数字(理性)と感情(人の想い)の両面をバランスよく取り入れること。どちらか一方に偏るのではなく、両輪として動かすことで、判断に厚みと説得力が生まれます。
経営者が「人の気持ち」と「会社の勘定」の両方を見つめる姿勢を持てば、社員も顧客も安心してついてきます。数字と感情の調和こそが、企業を持続的に成長させる判断力の源泉だと確信しています。
まとめ:決断力が経営者の人生と企業を動かす
迷いを糧に未来を切り拓く
経営者にとって迷いは避けられません。大切なのは、その迷いを否定するのではなく、成長の材料として活かす姿勢です。迷いがあるからこそ真剣に考え、悩むからこそ自分の軸が磨かれていきます。
私自身も、多くの場面で迷いに立ち止まった経験があります。しかし振り返ると、その迷いがあったからこそ学びが深まり、新たな挑戦へのエネルギーに変えることができました。「迷う=弱さ」ではなく、「迷う=未来をより良くしたい気持ちの表れ」なのです。
経営者が迷いを受け止め、それを糧に決断へと昇華できれば、企業も組織も次のステージへ進みます。迷いは経営者の敵ではなく、未来を切り拓くための師。その視点を持つことが、持続的な成長への第一歩になるのです。