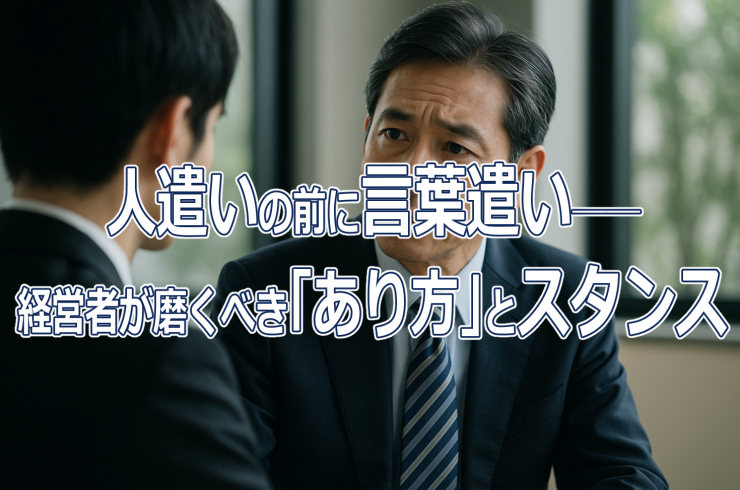【人遣いの前に、言葉遣い】
改善でなく、革新
働き方でなく、働き様
生き方でなく、生き様
やり方でなく、あり方
スキルより、スタンス
現状延長線上でなく
飛び移る
アクセル踏み込むでなく
シフトアップ
方法テクニックでなく
ものの見方考え方捉え方
経営者・リーダーとしてこう問いたい— ふさぽ@経営者 (@future_support) September 2, 2025
なぜ「人遣いの前に言葉遣い」なのか?
経営者の言葉が組織文化を形づくる
経営者の口から出る言葉は、単なるコミュニケーション手段ではありません。それは社員にとって「会社の価値観」を象徴するものです。たとえば「挑戦を歓迎する」という姿勢を言葉で示すリーダーのもとでは、新しいアイデアが自然と生まれやすくなります。一方で、「失敗するな」という言葉が繰り返される組織では、社員は安全策に走り、やがて停滞が常態化してしまいます。
つまり、経営者の言葉は組織全体の文化を形づくる“型”になるのです。私自身が関わってきた企業でも、経営者の言葉遣いが変わることで社員の雰囲気が一気に前向きに変化する場面を幾度も経験しました。言葉を磨くことは、会社全体の未来を磨くことにつながるのです。
言葉遣いが信頼関係を左右する理由
経営者と社員との関係は、突き詰めれば「信頼」で成り立っています。その信頼を築くうえで決定的な役割を果たすのが、日々の言葉遣いです。何気ない一言でも、社員は「自分を大切にしてくれているか」「尊重されているか」を敏感に感じ取ります。
例えば、同じ内容を伝える場合でも「早くやれ!」と強く言えば反発心を招きますが、「助かるよ、早めにお願いできるかな」と伝えれば協力的な空気が生まれます。言葉ひとつで社員の心の温度は大きく変わるのです。
私のこれまでの経験でも、厳しい局面を乗り越えられる会社と、そうでない会社の違いは、経営者が社員にどんな言葉をかけているかに大きく左右されていました。信頼を育む言葉を積み重ねてこそ、組織は一枚岩となり、困難にも立ち向かえるのです。
「改善」ではなく「革新」を選ぶ視点
現状維持がもたらすリスク
「現状維持でいい」という言葉ほど、組織を静かに衰退へ導くものはありません。経営の世界において、環境は常に変化しています。顧客のニーズ、競合の動き、技術革新――これらは待ったなしで進んでいきます。そんな中で「改善」で留まってしまうと、他社が「革新」で飛び越えてくるのです。
私が関わってきた企業の中にも、長年の成功体験に安心して現状を変えなかった結果、数年でシェアを大きく落としたケースがありました。一方で、小さな挑戦を積み重ね、思い切って新しい事業モデルに舵を切った会社は、逆境をチャンスに変えて成長していました。
現状維持は一見「安全策」に思えても、実際は「最大のリスク」になり得ます。経営者に必要なのは、改善ではなく革新を選び取る勇気なのです。
革新を生み出すリーダーの思考法
革新を生み出すリーダーには共通点があります。それは「できない理由」ではなく「どうすればできるか」を問い続ける姿勢です。環境の変化に対しても、「もう無理だ」と諦めるのではなく、「ここに新しいチャンスがある」と視点を切り替えられる柔軟さを持っています。
また、革新は必ずしも大規模なものとは限りません。日々の会議での問いかけや、社員への言葉ひとつからも芽生えます。「そのやり方は正しいか?」「もっと違う角度から見られないか?」と投げかけることで、社員が発想を広げ、結果的に大きな変化につながるのです。
私自身の経験でも、革新を起こすリーダーは「現状を疑う目」と「未来を描く目」の両方を持ち合わせていました。その二つの視点を意識的に使い分けることが、次のステージを切り開く原動力になるのです。
働き方より「働き様」──スタンスが未来を決める
やり方よりあり方が問われる時代
これまでの経営は「やり方」、つまり効率的な方法や正しいプロセスを追い求めることに重点が置かれてきました。しかし、いまの時代に求められているのは「あり方」です。リーダーがどんな姿勢で社員や社会に向き合っているのか、その在り様が人を動かし、共感を生むのです。
社員は上司の言葉や行動を敏感に見ています。たとえば「社員を大切にする」と口で言いながら、裏では数字だけを追い求める経営者に、心からの信頼は生まれません。一方で、苦しい局面でも「みんなで乗り越えよう」と自ら行動で示す経営者には、自然と人がついてきます。
つまり「やり方」より「あり方」が組織の持続力を決めるのです。方法論を学ぶよりも、まず自分のスタンスを磨くこと。それがこれからのリーダーに不可欠な資質だと強く感じています。
スキルよりスタンスが評価される背景
現代のビジネス環境は、変化が激しく予測困難です。そうした中で注目されているのが、専門的なスキル以上に「スタンス」、つまり物事に取り組む姿勢や考え方です。スキルは学べば身につきますが、スタンスはその人の価値観や生き様からにじみ出るもの。だからこそ、経営者やリーダーの評価はスタンスに大きく左右されるのです。
実際、社員が「この人についていきたい」と思うのは、経営者の持つ知識量よりも、その誠実さや責任感、挑戦に向かう前向きな姿勢です。失敗を恐れず挑み続けるリーダーの背中は、何よりの教育であり、組織全体の雰囲気を変えていきます。
私自身も講演やコンサルティングで「リーダーの姿勢が社員に与える影響」を数多く目にしてきました。結局のところ、スキルは一時の武器にすぎませんが、スタンスは人を惹きつけ、組織を持続的に成長させる基盤となるのです。
シフトアップの経営──アクセル全開からの脱却
経営の「延長線思考」の限界
多くの経営者がつまずくのは、「これまでうまくいった方法を続ければ大丈夫」という延長線思考です。しかし、変化のスピードが速い時代において、昨日の成功法則が今日の足かせになることは珍しくありません。
たとえば、ある製造業の企業では、長年の主力商品に固執しすぎた結果、新しい市場に適応できず、気がつけば競合に大きく引き離されていました。延長線上の発想は、現状を守ることに安心感を与えますが、同時に挑戦の芽を摘んでしまうのです。
経営に必要なのは「線を伸ばす」発想ではなく、「線から飛び移る」発想です。つまり、過去の延長ではなく、未来を切り拓く大胆なシフトが求められています。現状維持は衰退の始まり、この言葉を私は現場で痛感してきました。
飛び移る勇気と次のステージへの挑戦
経営のステージを変えるには、「飛び移る勇気」が欠かせません。延長線上で走り続けるのではなく、まったく新しい視点や市場へとシフトする。その決断にはリスクも伴いますが、挑戦なくして成長はありません。
私がご一緒したある企業では、既存事業が安定しているうちに思い切って新分野へ投資しました。周囲からは「無謀だ」とも言われましたが、数年後にはその事業が主力へと成長し、会社全体を支える柱になりました。経営者の「飛び移る」判断がなければ実現しなかった成果です。
もちろん、飛び移るには準備が必要です。現状をしっかり分析し、次に踏み出すべき方向を見極める。そして、信念をもって「やる」と決断する。社員はその姿に安心と覚悟を感じ、挑戦に力を合わせるのです。リーダーの勇気ある一歩が、組織全体を次のステージへと導きます。
方法論より「ものの見方・考え方・捉え方」
テクニック偏重からの脱皮
経営の現場では「どうやるか」という方法論やテクニックが注目されがちです。しかし、それだけに頼ると行き詰まりやすいのも事実です。なぜなら、テクニックは一時的に効果を発揮しても、状況が変われば通用しなくなるからです。
私が見てきた経営者の中にも、流行の手法や最新のツールを導入することに熱心な方がいました。ところが、肝心の考え方や目的が定まっていなかったため、社員は振り回され、結局は成果につながらなかったのです。
大切なのは、テクニックを支える「土台」としてのものの見方や捉え方を磨くことです。方法論はあくまで手段に過ぎません。根っこにある考え方がしっかりしていれば、どんな状況にも応じて最適な方法を選び取れるようになります。リーダーが本当に磨くべきは、流行のテクニックではなく、自らの視座なのです。
経営者が持つべき本質的な視座とは
経営者に求められるのは、表面的な方法論ではなく「本質を見抜く視座」です。売上や数字の増減といった結果だけを追うのではなく、その背後にある顧客の変化や社員の思いを掴む目を持つことが不可欠です。
例えば、業績が落ち込んだ時に「もっと営業を強化せよ」とだけ指示するのは短絡的です。本質的な視座を持つリーダーなら、「そもそも顧客が何を求めているのか」「提供価値が時代に合っているのか」と問い直します。その問いこそが新しい戦略や革新につながるのです。
私自身が支援してきた企業でも、経営者が「数字の奥にある意味」を捉えた瞬間に、組織の方向性がガラリと変わった場面を数多く見てきました。本質を問う視座は、迷いの多い時代にこそ経営者に必要な羅針盤となるのです。
まとめ:経営者が磨くべき「言葉遣い」と「あり方」
リーダーの言葉が未来を拓く
リーダーの言葉は、未来を切り拓く力を秘めています。何気ない一言が社員の背中を押し、挑戦への一歩を踏み出させることがあります。逆に、ネガティブな言葉は、組織全体を萎縮させてしまうこともあるのです。
「できるかどうか」ではなく「どうすればできるか」と言葉を変えるだけで、社員の思考は前向きにシフトします。リーダー自身が発する言葉を意識的に選ぶことで、組織の雰囲気は大きく変わり、未来に向かって動き出すのです。
私自身の体験でも、経営者が言葉を変えた瞬間に、社員の表情が和らぎ、会議の空気が一変した場面を幾度も見てきました。未来を拓くのは戦略や仕組みだけではありません。リーダーの言葉が社員の心を照らし、その光が未来を形づくるのです。
本質を問う経営姿勢が組織を変える
経営者が日々の意思決定で大切にすべきは、「何をすべきか」という方法論ではなく「なぜそれをするのか」という本質的な問いです。本質を問う姿勢があるかどうかで、組織の在り方や成長の方向性は大きく変わってきます。
例えば、コスト削減を進める場合でも、単に経費を抑えることが目的なのか、それとも社員や顧客にとって本当に価値ある資源配分を実現するためなのか。この問いかけがあるだけで、現場の理解度や実行の質はまったく違ったものになります。
私が支援してきた企業でも、経営者が「数字のため」ではなく「使命のため」という視点で物事を語ったとき、社員の心に火がつき、行動が変わりました。本質を問う経営姿勢は、組織を単なる作業集団から「志を共有するチーム」へと進化させる力を持っているのです。