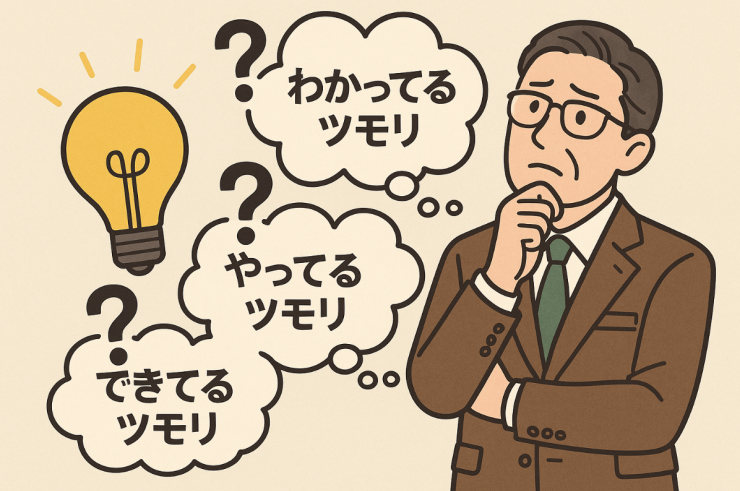何度も伝えたい「つもり病」
わかってるツモリ、やってるツモリ、できてるツモリ
自分では頑張ってる
が、自分の都合のいいよう、我流で空回り
成果や実績をだしている経営者には、「もったいない」と映る
自己満足でなく〈他者感動〉
相手の笑顔が、ジブンの笑顔
『相手から見てどうか』問い続けタイ— ふさぽ@経営者 (@future_support) August 28, 2025
「つもり病」とは何か?経営者が陥りやすい落とし穴
経営者の皆さんとお話ししていると、よく耳にするのが「やっているつもり」「伝えているつもり」「分かっているつもり」といった言葉です。私はこれをまとめて「つもり病」と呼んでいます。
一見、前向きに努力しているように見えても、実際には成果につながらず、周囲からは「空回り」に映ってしまう。このギャップこそが経営にとっての大きな落とし穴です。
なぜなら、経営の世界は“アマチュアの努力”ではなく“プロとしての結果”で評価されるからです。「頑張っています」だけでは社会は認めてくれません。社員も取引先も、実際の成果や変化を見て判断するのです。
私自身も若い頃、必死に走り回っているのに「成果がともなっていない」と先輩経営者から指摘された経験があります。その時は悔しかったですが、今振り返れば“つもり病”にかかっていたと言えます。
「つもり病」は誰しもかかる可能性があります。しかし、それを自覚し、改善していけるかどうかで経営者としての成長が決まります。
わかってるつもり、やってるつもり、できてるつもり
「わかってるつもり」という言葉の裏には、実は深い盲点があります。知識として耳にしたことがある、経験がある──それだけで「理解した」と思い込んでしまう。しかし、理解と実践の間には大きな溝があるのです。
さらに「やってるつもり」。これは実際の行動と成果が結びついていない典型例です。動いている感覚はあるのに、外から見れば進展が乏しい。経営の現場ではよくある光景です。
そして「できてるつもり」。これは最も危険です。結果が出ていないにもかかわらず、自己評価だけが高くなり、改善の機会を自ら閉ざしてしまう。社員や顧客からすれば、これほど不安なことはありません。
経営者がこの“三つのつもり”に陥ると、周囲とのギャップはどんどん広がります。経営は独り相撲ではなく、相手にどう届き、どう感動を与えるかが肝心です。
我流で空回りする危険性
経営の現場では、「自分なりのやり方」で突き進む方をよく見かけます。もちろん独自の工夫や創意工夫は大切ですが、それが“我流”に偏ると、成果を阻む落とし穴になります。
私自身、若いころ「誰にも負けないくらい努力している」という自負がありました。ところが先輩経営者からは「水野くん、それは空回りやで」と言われたことがあります。当時は悔しくもありましたが、今にして思えば我流が強すぎて、周囲が見えていなかったのです。
経営者にとって危険なのは、頑張っている自分に酔ってしまうこと。成果が出ていなくても「自分は正しい」と思い込むと、改善や学びの機会を逃してしまいます。社員やお客様からすれば、必死さは伝わっても“感動”にはつながらない。これが我流の怖さです。
だからこそ「相手から見てどうか」を常に問い直す必要があります。我流ではなく、他者の視点を取り入れること。それが経営の質を高め、空回りを防ぐ道となります。
成果を出す経営者と「つもり病」経営者の違い
自己満足にとどまる人の特徴
“つもり病”にかかる経営者の多くは、成果ではなく「自己満足」で安心してしまいます。例えば「社員に伝えたから大丈夫」と思い込む。でも実際には、社員が理解して動いていなかったり、顧客に価値が届いていなかったりすることが少なくありません。
このタイプの経営者に共通するのは、評価の基準が「自分側」にあることです。「自分はよくやった」「これだけ時間をかけた」「精一杯取り組んだ」といった主観的な達成感に依存してしまうのです。
しかし経営は、相手からどう見えるかがすべてです。社員が動かなければ成果にはつながらず、顧客が感動しなければリピートも紹介も起きません。自己満足で終わってしまうと、数字や実績に反映されず、やがて周囲からの信頼を失うことになります。
つまり、自己満足型の経営は「やっているのに成果が出ない」という悪循環を生み出します。これを断ち切る第一歩は、自分ではなく“相手”を基準に物事を見直すことです。
成果を積み上げる人の視点
成果を出し続ける経営者に共通しているのは、「自分ではなく相手を基準に考える」姿勢です。社員や顧客がどう感じるか、どう動くかを常に意識して行動しているのです。
例えば、社員に指示を出す際も「伝えたつもり」で終わらず、相手が理解して動けるかを確認します。顧客にサービスを提供する際も、「売ったから終わり」ではなく、その後の満足度や再購入につながるかを追いかけます。
成果を積み上げる経営者は、目に見える“数字”と目に見えない“感情”の両方を重視しています。数字で成果を測り、感情で関係をつなぐ。この両輪を回すことで、着実に信頼と実績を積み重ねていきます。
私がご一緒したある経営者も、毎日の会議で必ず「この取り組みは相手の喜びにつながっているか?」と問いかけていました。その習慣こそが、売上や社員の成長につながり、結果として業績を押し上げていたのです。
つまり、“成果を積み上げる視点”とは、常に相手に焦点を当て、自己満足ではなく他者感動を追い求める姿勢にほかなりません。
経営における〈他者感動〉の力
相手の笑顔が、自分の笑顔につながる理由
経営の本質は「相手の喜びを自分の喜びに変えること」にあります。社員や顧客の笑顔を見たとき、経営者自身も自然と笑顔になる。この循環が、企業の成長を持続させる原動力になります。
一方で、自己満足にとどまる経営では、この循環が生まれません。「自分は頑張った」と思っていても、相手が笑っていなければ、そこには感動も成果もありません。むしろ温度差が広がり、社員のモチベーション低下や顧客離れを招いてしまうのです。
私がご一緒したある経営者は、常に「社員の笑顔が会社の力だ」と口にされていました。社員が生き生きと働ける環境を整えた結果、顧客満足度が上がり、売上も着実に伸びていったのです。相手の笑顔が広がることで、自分も幸せを感じ、それがさらに良い行動につながる。まさに好循環です。
経営者は孤独になりがちですが、「相手の笑顔=自分の笑顔」という視点を持つだけで、日々の行動の意味が変わります。これこそが〈他者感動〉の力なのです。
「相手から見てどうか」を問い続ける習慣
経営者として成果を積み重ねるためには、「自分がどう思うか」ではなく「相手から見てどうか」を問い続ける習慣が欠かせません。
社員に指示を出すときも、「伝えたかどうか」ではなく「相手が理解して動ける状態になったか」。顧客に商品やサービスを提供するときも、「提供したかどうか」ではなく「相手に価値が伝わり、満足や感動が生まれたか」。この視点を持つだけで、経営の質は大きく変わります。
私も研修や講演の場で、「わかったつもりで終わっていないか?」と必ず自分に問い直すようにしています。伝えた内容が参加者の表情や行動にどう影響しているかを観察することで、本当に届いているかどうかを確認できるのです。
「相手から見てどうか」を問い続ける習慣は、自己満足を超え、他者感動へと導く羅針盤になります。経営者がこの習慣を持ち続けることこそ、組織を動かし続ける大きな力になるのです。
「つもり病」を脱却するための実践ポイント
行動を数字と習慣で客観視する
“つもり病”を脱却するために、まず取り組むべきは「行動の客観視」です。自分の主観だけでなく、数字と習慣という客観的な物差しを持つことが大切です。
たとえば「営業に力を入れているつもり」でも、実際には訪問件数や成約率の数字が伸びていなければ成果にはつながっていません。数字は冷静に現状を映し出し、自己満足を打ち破る鏡になります。
加えて、成果を生むのは一度の行動ではなく、継続した習慣です。毎日の行動を振り返り、どんな習慣が成果に結びついているか、逆にどんな習慣が空回りを生んでいるかを確認することで、改善の糸口が見えてきます。
経営者は孤独な立場だからこそ、自分の行動を甘く評価してしまいがちです。だからこそ「数字と習慣」を基準に置く。これが、つもり病を克服し、確実に成果を積み上げていく第一歩となります。
他者の声を鏡にするフィードバックの重要性
経営者にとって最も怖いのは、周囲の声が聞こえなくなることです。自己満足に陥ると、無意識のうちに耳障りの良い意見だけを受け取り、厳しい指摘を遠ざけてしまいます。これこそ“つもり病”を長引かせる最大の要因です。
成果を出す経営者は、常に他者の声を鏡として活用しています。社員の率直な意見、顧客の反応、時には取引先や同業者からの苦言さえも、自らを映し出す貴重なフィードバックと捉えるのです。
私自身も講演や研修を終えたあと、必ずアンケートや感想に目を通します。自分では「伝わった」と思っていても、参加者から「わかりづらかった」と書かれていれば、それは改善のサイン。相手の声に耳を傾けることで、成長のチャンスを得ることができます。
フィードバックを拒む経営は停滞します。しかし、素直に受け止めて改善を重ねれば、必ず組織は前進します。他者の声は、ときに耳が痛いものですが、それこそが“つもり病”を治す最良の薬なのです。
まとめ:経営者が磨くべきは自己満足ではなく〈他者感動〉
人を動かすリーダーに必要な視点
経営者に求められるのは、自己満足にとどまらず「人を動かす視点」を持ち続けることです。経営は一人で完結するものではなく、社員や顧客、取引先など多くの人が関わって成り立っています。その人たちが共感し、心を動かされてこそ、初めて成果が形となって現れるのです。
リーダーとして必要なのは、「自分がやったかどうか」ではなく「相手がどう感じたか」「どんな行動を引き出せたか」を軸に考える習慣です。この視点を持つ経営者は、自然と組織の力を引き出し、成果を積み重ねていきます。
自己満足で終わるリーダーと、他者感動を生むリーダー。その差はわずかなようでいて、長期的には大きな違いとなって現れます。まさに“わかってるつもり”が一番危険であり、“相手から見てどうか”を問い続けることが、真に人を動かす経営者の条件なのです。
豊かな経営人生を築くための心構え
経営者として歩む人生は、成果や数字だけで評価されるものではありません。大切なのは、その過程でどれだけ人の心を動かし、共に喜びを分かち合えたかです。相手の笑顔を自分の喜びと感じられるかどうか──ここに経営人生の豊かさが宿ります。
“つもり病”にとらわれている間は、自分の努力ばかりに意識が向き、周囲との温度差に気づけません。しかし「他者感動」を基準にすれば、努力の方向性が整い、信頼や感謝が積み重なっていきます。その結果、経営者自身の人生も、より満ち足りたものとなるのです。
私自身も、経営者の方々と向き合う中で常に学ばせていただいています。成果はもちろん大事ですが、最後に残るのは人とのつながりや笑顔です。経営は仕事であると同時に、志を形にする営み。だからこそ「相手から見てどうか」を問い続け、〈他者感動〉を追い求める姿勢が、豊かな経営人生の礎になると確信しています。