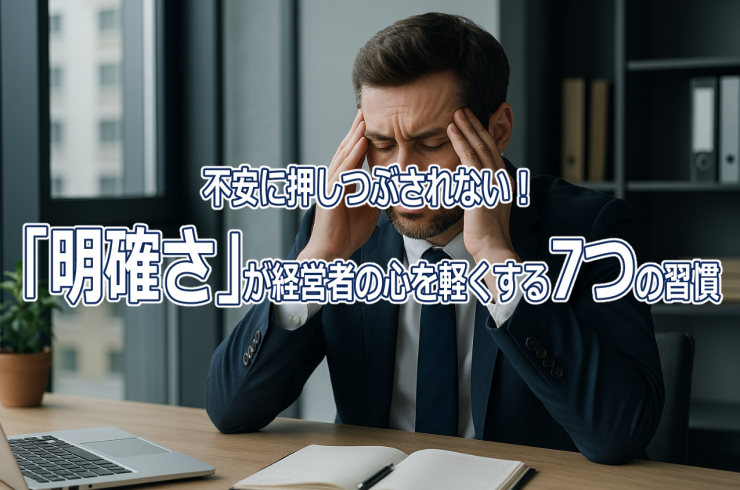【不安】
うまくできるだろうか
自分でいいのだろうか
もやもや、ぐるぐる、ぎゅうぎゅう、
と、考えてる時ってあるよね
ココで大事っ‼️
【明確さは力なり】
①書き出す
②人に言ってみる
③入力する
④一人録音する
⑤問いをもらう
⑥片付ける
⑦身なり整える
あなたのスッキリへの打開策
聴きたいな— ふさぽ@経営者 (@future_support) August 13, 2025
経営者を悩ませる「不安」とは何か?
経営者であれば誰しも「不安」と向き合う場面を避けて通れません。
「うまくできるだろうか」「自分でいいのだろうか」という問いが頭の中でぐるぐる回り、もやもやとした感情に押しつぶされそうになることもあるでしょう。これは決して経営初心者だけの問題ではなく、規模が大きくなればなるほど責任も重くなり、不安の影はついて回ります。
不安は放っておくと、判断を鈍らせたり、行動の一歩を遅らせたりする要因となります。結果としてチャンスを逃し、経営そのもののスピード感を失うことにもつながりかねません。
私自身も経営の現場で何度も経験しました。特に新しいチャレンジをするとき、あるいは社内の大きな変化に直面したとき、不安は必ず顔を出します。だからこそ、経営者にとって「不安」との付き合い方を学ぶことは、事業を継続的に伸ばしていくために欠かせないテーマなのです。
もやもや・ぐるぐる思考が生まれる背景
経営者が感じる「もやもや」や「ぐるぐる思考」には、いくつかの共通した背景があります。
第一に、情報量の多さです。経営者は日々、数字の動きから人材の状況、市場の変化まで膨大な情報を処理しています。その中で、整理しきれないまま抱え込むと、頭の中で何度も同じことを繰り返し考えてしまうのです。
第二に、責任の重さがあります。社員や顧客、取引先など、多くの人の生活や未来が自分の判断にかかっているというプレッシャーは、常に心に影を落とします。迷いが生じると「自分でいいのだろうか」と不安が強まり、堂々巡りの思考に陥りやすくなります。
第三に、未来が不透明であること。経営は常に変化の連続で、先が見えない中で決断を迫られる場面が少なくありません。答えがひとつに定まらない状況こそ、もやもやを増幅させる最大の要因となります。
こうした背景を理解するだけでも、「自分だけが弱いのではない」と気づけるはずです。不安や迷いは、経営者として成長する過程で誰もが通る道。むしろ、真剣に事業と人に向き合っている証とも言えるのです。
不安が判断や行動に与える悪影響
不安そのものは自然な感情ですが、放置すると経営に深刻な影響を与えることがあります。
第一に、判断の質が低下する ことです。不安が強いと、冷静な分析よりも感情に引きずられやすくなります。「最悪のシナリオばかり想定してしまう」「小さなリスクを過大評価してしまう」といった心理が働き、本来なら挑戦すべき場面で一歩を踏み出せなくなるのです。
第二に、行動が遅れる ことです。頭の中で「やるべきか、やめるべきか」と堂々巡りを繰り返すうちに、時間だけが過ぎていきます。経営の世界では、意思決定のスピードが競争優位を左右します。行動の遅れは、結果的に機会損失を招いてしまいます。
第三に、周囲への影響 です。経営者が不安を抱えたまま迷い続けると、社員や関係者にもその空気が伝わります。「社長が不安そうにしているから自分たちも心配だ」とチーム全体の士気が下がり、組織のパフォーマンスに直結してしまうのです。
つまり、不安はただの気持ちの問題ではなく、経営資源の一つである「時間」と「人材」にも悪影響を及ぼす存在なのです。だからこそ、不安に飲み込まれない工夫が求められます。
「明確さは力なり」──不安を軽くする鍵
不安を抱えているときに共通しているのは、「曖昧さ」が心を占めている状態です。
やるべきことが分からない、優先順位がはっきりしない、あるいは自分の役割に自信が持てない。こうした曖昧さは、不安を必要以上に大きくしてしまいます。
ここで大切なのが、「明確さは力なり」 という考え方です。
目標が明確になれば、そこに至るまでの道筋を描きやすくなり、余計な迷いが減ります。課題が明確になれば、解決に向けた具体的な行動を起こすことができます。明確さは、経営者にとって最大の「精神的エネルギー」となるのです。
私自身、経営の現場で不安に押しつぶされそうになったとき、必ず「まず明確にする」ことを心がけてきました。書き出す、話してみる、整理する…。どんな小さな一歩であっても、不安を減らすには「曖昧さを具体化する」ことが何よりの特効薬になります。
明確さを得ることで、不安は完全に消えるわけではありません。しかし「向き合える不安」に変わり、行動につながるエネルギーへと変換されていくのです。
曖昧さが不安を大きくする理由
人は「分からないもの」に直面したとき、不安を強く感じやすいと言われています。経営者にとっては、未来の業績、市場の変化、人材の成長など、不確実性に満ちた要素が日常的に存在します。この不確実性こそが「曖昧さ」であり、不安の温床なのです。
たとえば、明日の売上が読めないとき、数字は頭の中でどんどん膨らみ、最悪の想定ばかりが大きくなります。社員の気持ちが見えないときも同じです。ちょっとした表情や反応を過度に解釈してしまい、不安が増幅します。
心理学的にも「不確実性は人のストレスを高める」と示されています。つまり、不安の正体は「できないこと」そのものではなく、「分からないこと」にあるのです。
だからこそ、経営者は曖昧さをそのまま放置せず、明確に言語化し、整理する必要があります。問題を小さく切り分ければ、解決の糸口が見えやすくなり、不安は次第に現実的で対処可能なものへと変わっていくのです。
明確さがもたらす心理的エネルギー
明確さを得ることは、単なる「安心感」を超えて、大きな心理的エネルギーを生み出します。
第一に、集中力が高まる という効果があります。目標や課題が明確になると、不要な思考の寄り道が減り、「今やるべきこと」にエネルギーを注ぎやすくなります。経営者にとってこれは、意思決定や行動のスピードを上げる大きな力となります。
第二に、自己効力感が高まる ことです。漠然とした不安を抱えていると「自分にはできないのでは」という無力感に陥りやすいのですが、やるべきことが具体化されると「これならできる」という感覚が戻ってきます。小さな達成の積み重ねが自信へと変わり、次の挑戦を後押しするのです。
第三に、周囲を巻き込む力が強まる ことです。経営者自身が明確な言葉で方針や課題を語れると、社員や関係者も安心し、同じ方向を向きやすくなります。リーダーの「明確さ」は、組織全体に伝播し、チームのエネルギーを高めていきます。
私自身の経験でも、悩みをノートに書き出し、課題を一つひとつ整理した瞬間、不思議と胸のつかえが下り、自然と「やってみよう」という気持ちが湧いてきました。明確さは、不安を抑えるだけでなく、前に進むための力に変わるのです。
心を整理する7つの習慣とは?
「明確さは力なり」を実践するためには、具体的な行動に落とし込むことが大切です。頭の中だけで考えていると、不安は大きくなる一方ですが、行動に移すことで思考は整理され、気持ちが軽くなります。
ここで紹介する7つの習慣は、私自身も現場で実践してきた方法であり、多くの経営者に効果を実感していただいているものです。難しいスキルや特別な準備は不要で、すぐに取り入れられるシンプルな工夫ばかりです。
これらを一度にすべて完璧に行う必要はありません。自分に合ったものから始めるだけで、不安の質が変わり、思考の流れがスッキリしていきます。大事なのは「行動してみること」です。
次の小見出しから、具体的に7つの習慣をひとつずつ見ていきましょう。
書き出すことで思考を可視化する
頭の中で考え続けると、不安や課題はどんどん膨らんでいきます。まるで霧の中を歩いているように、何が本当の問題なのかも見えにくくなるのです。そこで有効なのが「書き出す」という習慣です。
ノートでもメモ帳でも構いません。思いつくままに、不安に感じていることや気がかりなことを箇条書きにしてみましょう。すると、頭の中で絡まっていた思考が目に見える形となり、「これとこれは同じ問題だ」「ここは意外と小さなことだ」と整理できるようになります。
私自身も、経営判断に迷ったときには必ずペンを持ち、紙に書き出してきました。書くことで不安がゼロになるわけではありませんが、「何が不安の正体か」を客観的にとらえる第一歩となります。
経営者は多くの決断を迫られますが、書き出す習慣を持つことで、もやもやを「課題」として扱えるようになり、次の行動に移りやすくなるのです。
人に話してフィードバックを得る
不安や悩みは、頭の中に閉じ込めているとどんどん膨らみます。しかし、人に話すことで思考は整理され、冷静にとらえ直せるようになります。経営者であっても、一人で抱え込まずに信頼できる相手に話すことは大きな意味を持ちます。
話す相手は、必ずしも専門家である必要はありません。同僚や家族、あるいは経営仲間でも良いのです。自分の言葉で悩みを説明する過程で、「実は自分の不安はここに集中していたのか」と気づくことがよくあります。さらに、相手からの率直な問いやフィードバックは、自分では見えなかった視点を与えてくれるでしょう。
私もかつて、ある大きな意思決定の場面で不安に押しつぶされそうになったとき、経営者仲間に話を聞いてもらいました。そのときの「その悩みは本質じゃないのでは?」という一言で霧が晴れたように視界が広がった経験があります。
経営者は孤独だと言われますが、だからこそ「人に話す」ことを習慣にすると、不安は力に変わっていきます。
入力や記録で客観視する
不安や悩みは、頭の中だけで考えていると主観に偏りがちです。そこで効果的なのが「入力や記録」という方法です。ノートに手書きするのも良いですが、パソコンやスマートフォンに入力してデータとして残すこともおすすめです。
文字にして保存することで、後から読み返すことができます。時間を置いて見直すと、「あの時は大げさに悩んでいたな」「同じことで何度も迷っているな」と、自分の思考の癖やパターンが見えてきます。これはまさに、自己理解を深める作業でもあります。
また、日記や経営ログとして残しておくと、自分の成長の軌跡にもなります。数か月前に悩んでいたことが、今は自然に解決できていることに気づくと、大きな自信につながるのです。
私自身も日々の記録を習慣にしていますが、「当時は不安で仕方なかったことが、今振り返ると小さな通過点だった」と感じることが少なくありません。記録は、未来の自分への励ましにもなるのです。
一人録音して自分の声を聴く
自分の考えや不安を声に出し、録音して聴き直すことは、意外なほど大きな効果をもたらします。頭の中で考えていることを言葉に変換すると、思考が整理され、客観的にとらえやすくなるのです。
録音して聴き返すと、「同じ言葉を繰り返している」「結論がはっきりしていない」といった、自分では気づきにくい癖が浮き彫りになります。これは一種の自己コーチングであり、自分で自分に問いかけるきっかけにもなるのです。
私自身も経営判断に迷ったとき、この方法を試したことがあります。録音を聴き返すと、「結局自分は挑戦したいと望んでいる」という本心がクリアに聞こえてきました。声に出すことで、思いの強弱やニュアンスがより鮮明になり、不安が整理されるのです。
経営者は孤独な存在であり、誰かに常に相談できるわけではありません。そんな時、この「一人録音」は手軽で強力なセルフマネジメントの手法になります。
他者から問いをもらう
自分一人で考えていると、どうしても思考は偏りやすくなります。そこで有効なのが「他者から問いをもらう」ことです。問いを投げかけてもらうことで、自分では気づかなかった視点に気づけたり、思考の枠を広げられたりします。
たとえば、「なぜそれが一番の問題だと思うのか?」「もし失敗しても大丈夫だとしたら、どうするか?」といった問いは、不安に凝り固まった思考をほぐすきっかけになります。問いかけは答えを与えるものではなく、考えの流れを新しく作り出す触媒なのです。
私自身、コンサルティングの場で経営者に問いを投げかけることがあります。すると「そういう見方をしたことはなかった」と驚かれ、不安が解消されることがよくあります。逆に、自分が問いを受けたときにも、同じように視界が開ける体験をしてきました。
経営者にとって、不安は孤独と結びつきやすいものです。しかし、誰かからのシンプルな問いによって、曖昧な霧が晴れ、明確さへとつながることがあるのです。
片付けて環境を整える
不安やもやもやを感じているとき、実は頭の中だけでなく「身の回りの環境」も乱れていることが少なくありません。デスクの上が書類でいっぱい、PCのデスクトップがアイコンで埋まっている──こうした状態は心のざわつきをさらに増幅させます。
逆に、机を片付けたり、不要な書類を捨てたりするだけで、不思議と気持ちが落ち着くものです。環境を整えることは、心を整えることに直結しています。
私も経営の現場で煮詰まったとき、まずデスク周りを整理します。すると頭の中の混乱までスッと収まり、自然と優先順位が見えてくるのです。特に、経営者は日々多くの情報を扱うため、物理的な整理はそのまま思考の整理につながります。
「片付け」は単なる掃除ではなく、不安に立ち向かう一つの実践的な方法です。環境が整えば、心も軽くなり、次の一歩を踏み出しやすくなります。
身なりを整えて気持ちを切り替える
不安を感じているときほど、身なりはおろそかになりがちです。しかし、身なりを整えることは単なる外見の問題ではなく、心の状態を立て直すための大切な手段です。
スーツに袖を通し、靴を磨き、髪を整える。そんな小さな行動が、自分に「よし、大丈夫だ」というメッセージを送ります。身なりを整えることは、自己肯定感を高め、内面に安心感を与える行為なのです。
私自身も、不安で気持ちが沈んでいるときにネクタイを締め直すことで「切り替えスイッチ」が入る経験をしてきました。社員や顧客の前に立つ経営者にとって、身なりを整えることは周囲への信頼感にもつながります。
「形から入るのは悪いことではない」。むしろ、形を整えるからこそ心も整うのです。経営者が自分を律し、前向きな一歩を踏み出すために、身なりを整えることは大切な習慣と言えるでしょう。
不安と向き合う経営者へのメッセージ
経営者にとって、不安は避けられないものです。むしろ挑戦を続ける限り、不安は常に隣り合わせにあります。しかし大切なのは、不安をなくすことではなく、不安とどう向き合うかです。
「明確さは力なり」。これは単なるスローガンではなく、実践を通じて実感できる言葉です。書き出す、人に話す、片付ける、身なりを整える…。どれも小さな行動ですが、その積み重ねが経営者の心を軽くし、前へと進む力を取り戻してくれます。
私自身、幾度となく不安に押しつぶされそうになりました。しかし、その都度「不安を整理する行動」を重ねることで、判断力や実行力を取り戻してきました。だからこそ、経営者仲間にお伝えしたいのです──「不安は敵ではなく、成長のきっかけに変えられる」と。
不安を感じたときこそ、今回の7つの習慣を思い出してください。あなたの心を軽くし、未来へ踏み出すエネルギーへと変えてくれるはずです。
明確さが未来を切り拓く
経営は常に変化と選択の連続です。将来の不確実性やプレッシャーは避けられませんが、そこで鍵を握るのが「明確さ」です。
明確さは、不安をゼロにする魔法ではありません。しかし、曖昧さを取り除き、自分が進むべき方向をはっきりさせることで、不安はエネルギーへと変わります。行動の指針がクリアになれば、経営者としての一歩は確実に軽くなるのです。
未来は誰にも予測できません。それでも「何を大切にし、どこへ進むのか」を明確にすることで、不安に押しつぶされるのではなく、不安を伴いながらも挑戦を続けられるのです。
私自身、多くの経営者と向き合ってきて感じるのは、明確さを持つ人は困難の中でも笑顔を失わないということです。明確さは迷いを減らし、人を惹きつけ、未来を切り拓く力になります。
だからこそ、不安を感じたときは思い出してください──「明確さは力なり」。その一歩が、あなたと組織の未来を大きく変えていくのです。