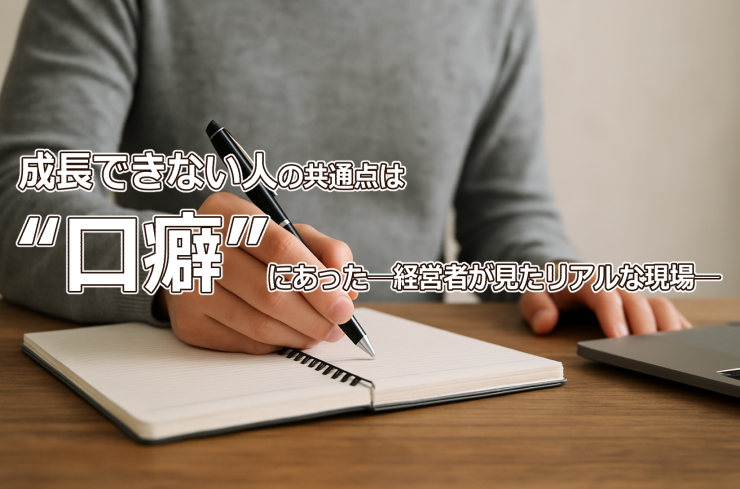もったいない
各社の採用や人材育成のご支援をしている中で出会う
成長に苦戦の人から感じる、口癖やインナートーク
「どうせムリだろう」
「どうせ変わらない」
「どうせ自分なんか」
目標や希望を抱いてものと、現実のギャップ
が、過去を嘆かず、口癖から一緒に見える未来に挑みたい
どうせ『なら』— ふさぽ@経営者 (@future_support) August 7, 2025
なぜ“口癖”に注目するのか?──思考と成長の関係性
インナートークが未来を制限する
「どうせ無理だろう」「どうせ変わらない」「どうせ自分なんか」──
私が現場で耳にするこうした“口癖”には、共通するある特徴があります。それは、自分自身の可能性をあらかじめ否定してしまう、いわば“内なる制限”の言葉であるということです。
経営者として、さまざまな人材育成の現場に立ち会ってきましたが、成長に苦戦している人には、ほぼ例外なくこの“インナートーク(心の中で自分にかける言葉)”が存在します。口に出していなくても、心の奥で何度も再生されている。そしてその内なる声が、行動を止め、挑戦の前に立ちはだかるのです。
「どうせ〇〇」とつぶやいた瞬間、人の脳はその仮定を事実として処理し始めます。やらない理由を正当化し、過去の失敗体験を引き出しては「やっぱりな」と結論づけてしまう。これでは、未来への一歩どころか、過去の延長線上でぐるぐる回るだけです。
私自身、若い頃にこうした言葉を無意識のうちに口にしていた時期がありました。「どうせ今さら変われへんやろ」と。でもね、その“口癖”が変わった瞬間から、行動が変わり、結果が変わっていった。だからこそ今、皆さんにも伝えたいのです。
「口癖は、未来を縛る呪いにもなれば、未来を開く鍵にもなる」
これは決して大げさな話ではありません。
口癖という小さな“習慣”が、思考をつくり、思考が行動を導き、行動が結果をつくる──私はこれを、何千人という現場で見てきました。
「どうせ無理」はどこから来るのか
「どうせ無理」──
この言葉の裏側には、経験や環境、そして過去の積み重ねによって刷り込まれた“思い込み”が潜んでいます。
たとえば、過去に何度か挑戦してうまくいかなかった経験。それが失敗体験として蓄積されると、人は知らず知らずのうちに「やっても無駄だ」「どうせ自分には無理だ」と自分に言い聞かせるようになります。
一見、自己防衛のようにも見えますが、実はこの“どうせ無理”という言葉は、現状にとどまり続けるための言い訳として機能しているのです。挑戦してまた傷つくぐらいなら、最初からやらないほうがいい。そんな無意識の“選択”が、成長の機会を奪ってしまいます。
現場で関わったある若手社員が、こうつぶやきました。
「僕なんて、高卒ですし、人前で話すのも苦手で…。どうせ無理ですよ」
しかし、数か月後──彼が自分の言葉に少しずつ気づき、「自分にできること」を語り始めたとき、まわりの目も変わり、本人も実績を出しはじめたのです。
つまり、「どうせ無理」という言葉は、過去の記憶や比較、そして自分に対する“思い込み”の集積によって生まれます。しかし同時に、それは“思い込みであるがゆえに、書き換えることもできる”という希望のサインでもあるのです。
私たち経営者は、社員や部下のこうした思考のクセにこそ、育成の突破口を見出すべきです。彼らの中にある「どうせ無理」の背景に目を向け、その裏にある“本当は変わりたい”という小さな灯を見逃してはいけません。
成長を止める“3つのどうせ”とは?
「どうせムリだろう」
「どうせムリだろう」──
これは、自らにブレーキをかける最も代表的な言葉です。
この言葉を口にする人は、一見すると“慎重派”にも映ります。しかしその実態は、「挑戦の放棄」「可能性の遮断」「未来への無関心」といった、非常に大きなリスクを抱えているのです。
経営の現場でも、会議で新しいアイデアが出た時に「いや、それムリちゃいますか」と、真っ先に否定から入る社員がいます。もちろん、リスクを見積もることは大切です。ただし、その言葉の背景に“過去の失敗”や“自信のなさ”がある場合、組織全体の挑戦意欲まで下げてしまうことがあります。
では、なぜ「ムリ」と決めつけてしまうのか?
理由は明確です。“成功のイメージ”が描けていないからです。達成のプロセスが想像できない、あるいは、達成している自分の姿が思い描けない。だから「ムリ」という言葉で思考をストップしてしまうのです。
私も昔、こんな経験がありました。初めて大きな経営案件にチャレンジした時、「今の自分にこの規模はムリやろ…」と、心の声がささやいてきました。でもね、その「ムリやろ」の一歩先に、「もしやれるとしたら、何が必要やろ?」と問いを変えてみたんです。すると、一気に視野が広がった。これは、口癖を変えることの効果を、私自身が実感した瞬間でした。
「ムリ」という言葉の裏には、「やったことがないから不安」「誰かに否定されたらどうしよう」という恐れが潜んでいます。しかし、その言葉を「どうすればできるだろう?」に言い換えるだけで、脳は“方法を探すモード”に切り替わるのです。
口癖は思考の習慣。
思考の習慣が変われば、行動が変わり、結果が変わる。
これは、経営でも人生でもまったく同じです。
「どうせ変わらない」
「どうせ変わらない」──
これは、変化への希望を自ら閉ざしてしまう言葉です。
この口癖を持つ人は、一見すると冷静に状況を見ているように見えるかもしれません。けれども、実は“過去の延長線”でしか未来を捉えておらず、自ら変化を止めてしまっているケースが多いのです。
「会社の風土は変わらない」
「上司は聞く耳を持たない」
「どうせ制度も戻るだけ」
そうした言葉が口をついて出るたびに、人は環境のせいにして、自分の力をどこかに置き去りにしてしまいます。
しかし、私がこれまで関わってきた組織の中で、本当に変化が起こった会社には、共通して「一人の想い」が起点になっていました。
ある中堅社員が、こんな言葉をくれました。
「どうせ変わらんって思ってたけど、水野さんの“まず自分が変わる”って話を聞いて、試しに小さなことからやってみたんです」
彼は毎朝の朝礼で、自分から先に声をかけ、後輩を立てて話を引き出すように変えた。それだけで、チームの空気が変わっていったんです。
結局、「変わらない」のではなく、「変えようとしていない」だけなのかもしれません。
特に組織においては、自分以外が変わるのを待っていても、永遠に何も変わらない。けれど、“自分”が変われば、まわりの見え方が変わり、行動が変わり、やがてチーム全体にも影響が及ぶ──私はそう信じています。
「どうせ変わらない」と言ったその瞬間に、未来は停止してしまいます。
けれど、「変わるかもしれない」と思った瞬間に、未来は動き出す。
その違いを生むのが、たった一言の“口癖”なんです。
「どうせ自分なんか」
「どうせ自分なんか」──
これは、自尊感情が下がったときに現れやすい、もっとも根深い口癖です。
私がこれまで多くの企業で出会ってきた社員の中でも、この言葉を発する人にはある共通点がありました。それは、期待されていないと“感じている”ということ。たとえ周囲が期待していても、本人が「自分にはそんな価値はない」と思い込んでいる状態では、その期待が届きません。
ある女性社員が、評価面談の場でこう言ったことがあります。
「どうせ私なんか、いてもいなくても同じですから」
正直、胸が詰まりました。こんなにも頑張っているのに、なぜそんなふうに自分を扱ってしまうのか。よくよく話を聞くと、過去に上司から認められなかった経験や、チームで浮いていた時期があったとのこと。
でもね、それを経て、私は彼女にこう伝えました。
「“自分なんか”じゃなく、“自分だからこそ”だと思って取り組んでみてほしい」
自己肯定感は、実は“結果”ではなく“プロセス”から生まれるものです。
小さな成功体験、小さな信頼の積み重ね──それが「自分には価値がある」と思える感覚を育てていきます。だからこそ、私たち経営者やリーダーは、そうしたプロセスに気づき、声をかける必要があるのです。
「どうせ自分なんか」と思っている人ほど、実は誰よりも変わりたいと思っている。
その小さな願いを見逃さず、寄り添い、照らし出す存在でありたい。
“自分を小さくする口癖”を、“未来を照らす言葉”へ──
その第一歩が、組織の空気を変え、やがて業績さえも変えていくと私は信じています。
なぜ口癖が変わると、人生が変わるのか?
脳の仕組みと習慣の影響
「口癖を変えるだけで、本当に人生が変わるのか?」
そう思われる方もいらっしゃるかもしれません。
しかし私は、数多くの経営現場と人材育成の場面で、「言葉の習慣」が人の思考・行動・成果にどれほど強く影響を与えているかを、何度も目の当たりにしてきました。
その根拠は、脳の仕組みにあります。
人の脳には「RAS(網様体賦活系)」というフィルターのような働きがあります。このRASは、私たちが日々使う言葉や意識していることに基づいて、“必要な情報”と“不要な情報”を選別してくれています。
つまり、「どうせ無理」「変わらない」「自分なんか」といった否定的な言葉を日常的に使っていると、脳は「その通りの現実」を探し出してしまうのです。挑戦のチャンスや、周囲の励ましにさえ気づかなくなってしまう。
逆に、「できるかもしれない」「少しでも進もう」「やってみよう」といった前向きな口癖を使うと、脳はそれに合わせて視界を広げ、可能性に気づけるようになります。
そして、もうひとつ大切なのは「習慣」です。
言葉は繰り返すことで、“無意識の信念”となります。1回のポジティブ発言ではなく、毎日の小さな積み重ねが、思考の質を変え、行動を変えていくのです。
たとえば私は、経営判断に迷ったときに、意識してこう自問するようにしています。
「どうすれば、うまくいく可能性を1%でも上げられるか?」
この口癖があることで、思考がストップせず、前向きな仮説を立てることができるんです。
“言葉が脳に影響を与え、脳が行動を導く”
この連鎖を意図的にデザインできるかどうかが、成果の差を生む鍵となります。
だからこそ──
「まずは口癖から」
私はそう提案したいのです。
自己暗示としての言葉の力
「どうせ無理」
「自分にはできない」
「また失敗するに決まってる」
こうした言葉は、誰かから言われるものではなく、ほとんどの場合、自分で自分に言っているものです。つまり、これは“自己暗示”です。そして厄介なことに、その暗示は思った以上に強力に私たちの行動を制限します。
心理学の世界では「セルフ・トーク(内的対話)」という言葉があります。
人は一日に6万回以上、自分自身に言葉をかけているとも言われており、その多くは無意識です。無意識に繰り返された言葉は、やがて“自分自身の真実”になっていくのです。
たとえば──
「私は人前で話すのが苦手だ」
そう何度も自分に言い聞かせていれば、本当に人前で話せなくなります。
逆に、「まだ上手くないだけ。場数を踏めばうまくなる」と言い続けていれば、苦手意識は薄れていき、自然と行動の質も変わっていきます。
私はこれを、経営者やリーダーの皆さんにもこう問いかけたいのです。
「あなたは、社員にどんな“自己暗示”を与えているか?」
部下やチームのメンバーが、「どうせ聞いてもムダ」「どうせやっても変わらない」と思ってしまう背景には、日々の言葉が関係している可能性があります。
だからこそ、まずは自分自身の口癖を整えること。
そのうえで、相手の“前提”をひらく言葉──
「○○さんなら、きっとできるよ」
「その挑戦、面白いやん」
そんな肯定的な“言葉の暗示”を周囲に贈ることが、チームの雰囲気を変え、成果を変えていくのです。
言葉は薬にも毒にもなる。
だからこそ、自分にかける“言葉のくすり”を、意識して選びたいものです。
「どうせ◯◯」から「どうせ“なら”」へ──言葉のリフレーミング
経営現場で起きた、言葉の変化による変化
「どうせ無理だろう」
「どうせ自分なんか」
そんな言葉に悩んでいた社員が、あるときふと、こう言い換えたのです。
──「どうせやるなら、楽しもうと思って」
私はその瞬間、思わず笑みをこぼしました。
これこそが、言葉の“リフレーミング(枠組みの再構築)”です。
同じ「どうせ」でも、前提を変えるだけで意味も結果もまったく変わってくる。これは経営現場において、何度も目にしてきた“変化の兆し”です。
ある地方の中小企業で、営業成績が伸び悩んでいた若手社員がいました。彼は何かにつけて「どうせやっても結果が出ないですから」と言っていました。でも、上司が彼の話に耳を傾け、「じゃあ、“どうせやるなら結果出したくない?”って言ってみてごらん」と促したんです。
最初は照れくさそうに口にしていた彼も、次第にその言葉を自分の“目標”として使い始めました。すると、数字が徐々に上がり始めた。なぜか?
それは、言葉の変化が、行動の意図と方向を変えたからです。
言葉は、自分自身への“命令”でもあります。
「どうせやってもダメだ」と言えば、脳はやる気を失い、力を抜きます。
「どうせやるなら意味ある時間にしたい」と言えば、脳はチャンスを探し始める。
この差は、1日では小さいかもしれません。
けれど、それが1週間、1か月、1年と続けば──とてつもない違いになります。
経営とは、数字だけを動かすものではありません。
人の“心の中の言葉”を動かすことでもあるのです。
「どうせやるなら」「どうせなら変えてみよう」
この“ひと言の変化”から、人生も、職場も、動き出すと私は確信しています。
小さな成功体験が意識を変える
「どうせ無理」「どうせ変わらない」──
そんな否定的な言葉を手放すために、最も効果的なのが“小さな成功体験”です。
人は、いきなり大きな目標に向かおうとすると、現実とのギャップに押しつぶされそうになります。特に、自己評価が低くなっている状態では、「やっても無理やろ」というインナートークが強く働きます。
そこで大切なのが、“とても小さな”達成感を積み重ねること。
私が関わったとある現場では、報連相がうまくいかずに孤立していた若手社員に対して、上司が「1日1回だけでいいから、誰かに話しかけてみようか」と提案しました。するとどうでしょう。最初の週はぎこちなかった彼が、2週目には自ら相談に行くようになり、3週目には後輩のフォローまで始めたのです。
この変化の鍵は、“できた自分”を自覚できたことです。
「やれば少し変わる」
その体感が、“どうせ”という口癖に歯止めをかけたのです。
実は、脳は「自分ができたこと」よりも、「自分がやらなかった理由」の方をよく覚えています。だからこそ、成功体験は意識して“記録し、言葉にして、振り返る”ことが必要です。
私もかつて、ある大きなプロジェクトで成果が出なかったとき、自分にこう問いかけました。
「今回はうまくいかなかったけど、その中で“唯一うまくいった1つ”は何だったか?」
たったそれだけで、次に進むエネルギーが湧いてきたのです。
つまり、「できたこと」に光を当てる習慣こそが、「どうせ無理」の影を薄くしていく処方箋なのです。
“ちょっとした変化”が、“大きな確信”に変わるとき、
人は自然と未来に向かって動き出します。
未来を拓くために、今すぐできる3つの実践
自分の口癖を書き出してみる
成長の一歩は、“自覚”から始まります。
その中でも、もっとも手軽で効果的な方法が「自分の口癖を言語化すること」です。
人は無意識のうちに、自分に対して同じ言葉を繰り返しています。
けれども、それが“無意識”である限り、変えることはできません。
まずはその言葉たちに、気づいてあげることが重要なのです。
おすすめは、1日の終わりに5分だけ時間を取り、「今日、自分がよく使った言葉」をメモに書き出すこと。
・どうせ無理
・めんどくさい
・なんで私ばっかり…
・まぁいいか
そんな言葉が並んでいるのを見て、自分でハッとする方も少なくありません。
逆に、「よし、やってみよう」「ありがたいな」「大丈夫やろ」など、前向きな口癖が並んでいれば、それはそれで自信になります。
ある若手経営者が、毎晩寝る前に「今日の自分語録」を3つメモする習慣を続けていました。最初はネガティブな言葉ばかりでしたが、数週間後には「やってみたら意外とできた」「自分、思ったよりも頑張ってた」と、自分を肯定する言葉が増えていたのです。
“言葉は、その人の人生観を映す鏡”です。
だからこそ、その鏡を一度のぞき込んでみる。
その行為そのものが、変化の起点になります。
まずは書き出してみる。
そこから見える“口癖の地図”が、あなた自身の思考と未来を教えてくれるはずです。
周囲のフィードバックを取り入れる
自分の口癖には、意外と自分では気づけないものです。
だからこそ、「他者からのフィードバック」が、自分の思考のクセに気づく絶好のチャンスになります。
たとえば、信頼できる同僚や上司、家族にこう聞いてみてください。
「私って、よく言ってる口癖ってある?」
この質問、ちょっと勇気がいります。
でも、返ってきた答えは、自分を変えるヒントになる可能性が非常に高いのです。
ある企業で実施された“相互フィードバックワーク”では、社員同士でお互いの口癖や発言の傾向を伝え合いました。すると、「○○さんって、すぐに“でも…”って言うよね」と指摘された社員が、それに気づいて言い換える努力を始めたことで、発言の質も周囲からの印象も大きく変わったのです。
大事なのは、「指摘された言葉=人格の否定」ではないという理解です。
それはあくまでも、“思考のパターン”へのフィードバック。
だからこそ、感情的にならず、素直に受け止めて、ひとつでも言い換えを試してみる。
フィードバックをもらうときのポイントは次の3つです。
“変わりたい”という意思を伝えること
→「変わりたいからこそ聞かせてほしい」と前置きするだけで、相手の伝え方も変わります。否定的な言葉をもらっても、まずは「ありがとう」で受け止めること
→反論したくなる気持ちをグッとこらえることが大切です。もらったフィードバックを“観察ポイント”として数日間意識してみること
→「あ、また“でも”って言ったな」と気づくこと自体が大きな一歩です。
“他人の目”という外側のレンズで、自分の思考を映してみる。
それは、自分自身では見えなかった“無意識のクセ”を炙り出し、
未来を拓くための大きなきっかけになります。
言葉の選び方を意識する場面を設ける
「言葉は変えようと思えば、変えられる」
そうは言っても、忙しい日常のなかで常に意識するのは難しい──そう感じる方も多いでしょう。
だからこそ大切なのが、“言葉を意識する時間”をあえて設けることです。
無理に24時間気を張る必要はありません。ポイントは、「短時間でも意識的な時間」をもつことです。
たとえば、こんな場面を意識するだけで、口癖の“精度”は大きく変わります。
おすすめの実践シーン
会議で発言する前の10秒間
→「否定から入っていないか」「誰かの意見を遮っていないか」をチェック。1on1の面談中
→相手の可能性を引き出すような“問いかけの言葉”を選ぶようにする。日報や週報を書くとき
→「できなかった」ではなく「次はどうするか」という前向きな表現を意識。朝礼や挨拶の場面
→「今日は忙しい」ではなく「今日はどこを工夫できるか」という言い回しに変えてみる。
このように、“言葉の選び方”を日常の中に組み込んでいくことで、自然とポジティブな口癖が身についてきます。
また、私はときどき「逆口癖ノート」を提案しています。
たとえば──
「めんどくさい」→「今ならチャンスやな」
「無理やろ」→「どこまでならできそうか?」
「私なんて」→「私だからこそできることがある」
こうした“変換パターン”をあらかじめ考えておくことで、いざというときに迷わず言い換えができます。
言葉は、環境を変えなくても“自分の内側”から変えられる最も強力なツールです。
だからこそ、毎日のなかに少しだけ“言葉の意識タイム”を設けてみませんか?