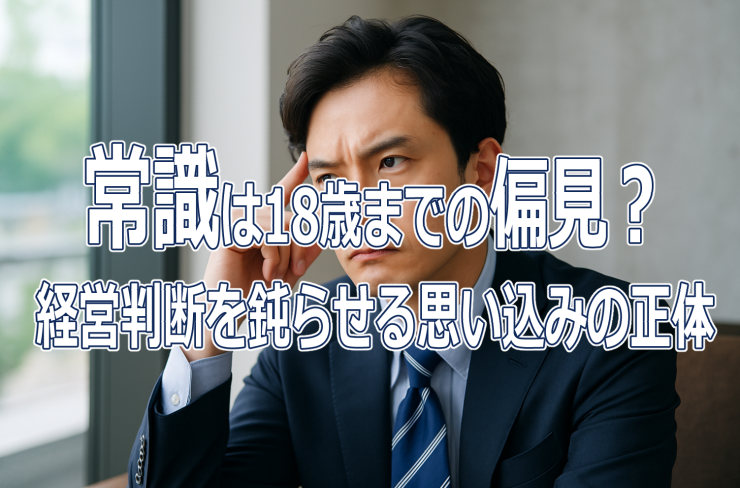【常識】
「それって、当たり前だよねぇ」
20代の頃、言葉に出さなくとも、よく感じていた
それが、あのアインシュタイン先生に学んで変わった
「常識とは何か?」
それは、18歳までに身につけた偏見のかたまりのこと
じょうしき'で'考える。ではなく、ジョウシキ"を"カンガエル
言霊との出会いは、宝— ふさぽ@経営者 (@future_support) July 16, 2025
「それ、当たり前やろ?」が口癖だった頃の私
若手時代に染みついた“常識”というフィルター
若い頃の私は、「それ、当たり前やろ?」と心の中でつぶやくことが多かったんです。
声に出さなくても、目の前の出来事に対して“常識フィルター”で判断してしまう。そんな自分が当時は正しいと思っていたんですね。
たとえば、会議で斬新なアイデアが出たとしても、「いや、それは現実的ちゃうやろ」と一刀両断。現場でトラブルが起きても、「それくらい考えたら分かるやん」と、相手の背景や状況を想像せずに決めつけていました。
もちろん、常識っていうのは社会をスムーズに回すために必要な側面もあります。でも、20代の私は“常識=正解”やと思い込んでたんです。しかも、その“常識”の正体が、自分の経験とか、育った環境とか、過去に教え込まれた価値観でできてることには、気づいてへんかった。
つまり、“正しい”と信じてたことが、実はただの“思い込み”やったんですよね。
アインシュタインの一言が、私の価値観をひっくり返した
「常識とは18歳までに身につけた偏見のかたまり」
ある時、書籍でふと目にしたアインシュタインの言葉に、頭をガツンと殴られたような衝撃を受けました。
「常識とは18歳までに身につけた偏見のかたまりである」
…なんちゅう表現や。
それまでの私は、「常識」ってのは“正しさ”や“基準”やと思ってたんです。でもこの一言で、常識が“正解”ではなく、“偏見”の可能性があると気づかされた。つまり、自分の中で当たり前やと思っていたことが、他人にとってはまったく当たり前じゃない。いや、それどころか思い込みでしかないかもしれへん、と。
経営というのは判断の連続です。そしてその判断の土台には、自分の「信念」や「経験」や、もっと言えば「常識」がある。でも、その常識が古かったり、ズレていたり、社会の変化に追いついてなかったとしたら…。その判断は、間違うてるかもしれんのです。
「自分の中の“当たり前”を、ちゃんと疑ってるか?」
アインシュタイン先生に、そう問いかけられたような気がしました。
その日から、私は“常識で考える”のをやめて、“常識を考える”ようになったんです。
“常識で考える”経営が、危うい理由とは?
経営判断を鈍らせる“見えない前提”の罠
「この判断、うちの業界では常識やから」
「それは昔からそういうもんやろ」
「まぁ、普通はこう考えるよね」
こんな言葉が社内で飛び交っていたら、ちょっと注意が必要です。
なぜなら、“常識で考える”ことは、無意識に「思考停止」を招くからです。
経営というのは、変化対応の連続です。ところが、“常識”というのはえてして「過去」に基づいています。つまり、いま現在やこれからに目を向けるのではなく、「昔こうだったから今もそうやろう」と、過去の枠組みで物事を判断してしまう。
特に、ベテラン経営者であればあるほど、この“見えない前提”に気づきにくい。なまじ経験がある分、それが“正解”として染みついてしまってるんですな。
でもね、時代は変わってるんです。
社会も価値観も、働く人のマインドも、お客様の期待も。
そこに、昔の“常識”をそのまま当てはめてしまうと、うまくいくどころか逆効果になることもあります。
私自身、かつて「それくらい自分で考えて動けよ」と言ってしまっていた。けれど、若手社員にとっては「勝手に動いたら怒られるかもしれない」「上司に確認しないといけない」っていう文化が常識だったりするわけです。
つまり、“常識”とは、自分が気づかぬうちに抱えている“思い込みの前提”なんですわ。
経営判断を誤るのは、情報不足よりも、こうした“無自覚な偏見”のほうがよっぽど多いように思います。
経営者が“ジョウシキを考える”べき3つの理由
柔軟性・創造性・人間力に直結する思考習慣
「常識で考えるな。常識を考えよ。」
これは、経営者として私が長年大切にしてきたひとつの信念です。
常識というのは便利です。判断のスピードが上がるし、説明しなくても済むし、組織をまとめる上でも“空気を読む”という点では有効かもしれません。でも、それに頼りきると、経営者として最も大切な能力を鈍らせてしまう。その理由を、今日は3つに分けてお話します。
① 柔軟性が失われる
常識を疑わず信じてしまうと、新しい状況や価値観に対して「NO」と言うクセがついてしまいます。「そんなやり方、聞いたことない」「それは非常識や」と否定から入ってしまうと、可能性の芽を自ら摘んでしまう。
変化の時代において、これは致命傷です。
② 創造性が育たない
常識とは、既存の枠組みです。その枠の中だけで考えていては、イノベーションは生まれません。むしろ「なんでそれが当たり前なんやろ?」と問い直すことが、新しい発想を生むんです。
たとえば、“上司が指示を出す”という常識を疑ったからこそ、“部下が自ら提案する文化”が生まれた会社もあります。
③ 人間力が磨かれない
常識に頼るというのは、自分の価値観や経験を絶対視しているということ。
でも、経営者に求められるのは「正しさ」よりも「柔らかさ」。相手の背景や価値観を尊重し、違いを受け止める器が、これからの時代のリーダーシップです。
私も、過去に“自分の当たり前”を部下に押しつけて、何度も失敗してきました。でもその失敗が、「あぁ、自分は常識で人を見てたんやな」と気づくきっかけになったんです。
だからこそ今は、判断に迷ったときこそ、「これは自分の常識か?社会の常識か?相手の常識か?」と、自問するようにしています。
「言霊」が経営を変える〜思考と言葉のアップデート術
口癖・言い回しを見直すだけで組織が動き出す
「ことばには魂が宿る」と言われるように、日本には“言霊”という考え方があります。
私も正直、若い頃は「何をスピリチュアルな…」とどこか斜に構えてました。でも今なら言えます。言葉は、経営そのものを動かす力があると。
とくに経営者の言葉、これが組織全体の空気や行動に直結するんですわ。
たとえば、こんな口癖、つい出てませんか?
「だから何?」
「お前の意見は聞いてない」
「もうええって、その話」
こんな一言で、どれだけ多くの“報告”“相談”“提案”の芽が摘まれているか…。
逆に言えば、「それ、教えてくれてありがとう」「よう気づいたなぁ」「で、君はどうしたい?」
たったそれだけで、部下は“聴いてもらえている”と感じ、主体的に動くようになるんです。
言霊の力を痛感したのは、自分の口癖を意識して変えたときです。
以前は「何回言ったら分かるんや!」が口癖やったんですが、今は「伝わったかどうか、一緒に確認してみようか?」に変えました。
たったこれだけで、空気が変わった。
部下が目を見て返事してくれるようになった。自分もイライラせんで済むようになった。
つまり、「常識を疑う」というのは、使う言葉を変えることでもあるんです。
言葉は、自分の思考を表す鏡でもありますから。
古い“言い回し”をそのまま使ってる経営者は、もしかすると“思考”まで古くなってるかもしれません。
常識のアップデートは、“言葉のアップデート”から始まる。
そう想っています。
まとめ:非常識こそ、新しい価値を生むヒント
常識からの脱皮が、リーダーの真価を育てる
「それって当たり前やろ?」
かつての私が、無意識に抱いていた“常識”という偏見。
でも、アインシュタインのあの言葉——
「常識とは18歳までに身につけた偏見のかたまりである」
この一言が、私の考え方を180度ひっくり返しました。
経営の世界は、日々変化しています。
それに対応するには、“柔軟さ”と“しなやかさ”が要ります。
その源が、「常識を疑う」という視点です。
「自分の“当たり前”は、他人にとってもそうか?」
「その言葉、10年前から変わってないんちゃうか?」
「この判断は、過去の成功体験からきてへんか?」
問い直すことで、はじめて“非常識”にチャンスが見える。
非常識こそ、未来の常識になり得る種なんです。
経営者とは、先を見通し、決断し、そして育む存在です。
だからこそ、「常識で判断する」人ではなく、
「常識を問い直せる」人であってほしい。
私自身、まだまだ“常識人間”になりかけることもあります。
けれど、そのたびに自分に問いかけます。
「それって、本当に“当たり前”か?」
この問いを忘れへんこと。
それが、経営者としての真価を育てる道やと、私は信じています。