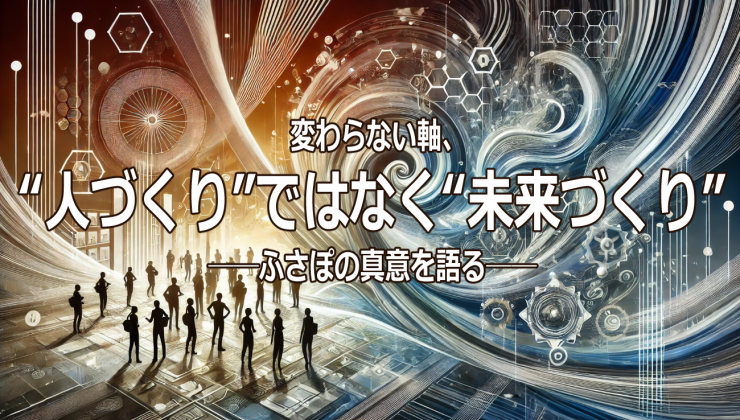この時期、聞かれる
「新人育成もしてるの?」
「経営者支援や、幹部育成じゃなかったの?」と
対象を、コロコロと変えてはいない
私の事業テーマは単なる人づくりではなく、《組織づくり、未来づくり》
ふさぽの意味は、Future SuPPort
新入社員やHRと一緒に『組織に変革の渦』を、巻き起こしたい— ふさぽ@経営者 (@future_support) March 29, 2025
なぜ今、「新人育成してるの?」と聞かれるのか?
支援対象に対する誤解とその背景
春になると、よく聞かれる言葉があります。
「最近は新人育成もされているんですね?」
「以前は経営者や幹部向けの支援だったのでは?」と。
確かに、外から見ると“支援対象が変わった”ように映るのかもしれません。しかし、私自身の中で軸がぶれたという感覚はまったくありません。
私が一貫して取り組んでいるのは「人づくり」ではなく「未来づくり」です。支援する立場として、組織や社会の“これから”をどう支えるか。そのために何ができるのかという視点が、常に土台にあります。
Future Supportという名前には、まさにこの「未来を支える」という想いが込められています。
カテゴリで見れば“新人育成”と“経営者支援”は対極にあるように感じられるかもしれませんが、どちらも未来づくりという文脈では同じ地平にあります。
新入社員は、これからの組織文化を担う起点でもあります。だからこそ、変革の渦を生み出すには、経営層だけでなく、現場の一人ひとりと向き合うことが重要なのです。
Future Supportの意味とは──名前に込めた想い
名前に込めた想いと未来志向の支援軸
私が活動の名称として「Future Support」という言葉を選んだのには、明確な理由があります。
一見すると、「未来を支える」というシンプルな意味に見えるかもしれません。しかしこの言葉には、「今この瞬間に関わる支援が、未来にどうつながるか」を常に意識していく姿勢が込められています。
支援というのは、目の前の課題を解決するだけでは不十分です。組織であれ、人材であれ、今手を加えることで“次にどんな景色が広がるか”を見通しておく必要があります。
Future Supportは、「未来の可能性に火を灯す支援」でありたい。だからこそ、関わる人がどんな立場であっても、支援のゴールは“目先の成果”ではなく、“その人や組織が進んでいく方向”にあります。
私にとってこの名前は、「支援者としての覚悟」を常に思い出させてくれる旗印でもあるのです。
“人づくり”ではなく“未来づくり”というスタンス
一過性の育成で終わらせない組織支援の考え方
「人づくり」と聞くと、多くの方が“スキルやマインドの強化”“研修や教育”といった具体的な取り組みを思い浮かべるのではないでしょうか。もちろん、それらも大切な要素です。ですが、私の中ではあくまで“手段のひとつ”であって、目的そのものではありません。
私が見ているのは、その人が育つことでどんな未来が、どんな組織が生まれていくのかというところです。つまり、「人をつくる」ことではなく「未来をつくる」ことを目指しているのです。
個人が成長することで、チームに対話が生まれ、現場に新しい視点が入り、やがて組織文化そのものが変わっていく。その変化の連鎖を起こしてこそ、未来づくりは本物になります。
だから私は、一人の成長が“点”で終わるのではなく、組織に波紋のように広がる“線や面”になる支援を心がけています。
それが、「人づくり」にとどまらない「未来づくり」というスタンスです。
新入社員も幹部も、組織変革の“起点”になれる
「誰からでも始まる」変革の渦の中心にあるもの
組織変革というと、「まずはトップから」と考える方が多いかもしれません。もちろん、経営層の姿勢や意思決定は大きな影響を与えます。しかし、私が現場で見てきた限りでは、変革の火種は、いつも思いがけないところから生まれます。
それは、新入社員かもしれません。
あるいは、管理職ではない中堅社員かもしれません。
そしてもちろん、幹部層から始まることもあります。
重要なのは「誰が起点か」ではなく、その起点が“渦”を生み出せるかどうかです。
Future Supportの支援では、立場や役職にとらわれず、一人ひとりが“未来に向けた問い”を立て、対話し、動き出すことを大切にしています。
組織に新しい風が吹くとき、そこには必ず“勇気ある誰か”の存在があります。新人であっても、たった一言の問いかけや、姿勢ひとつで、周囲の空気が変わることがあるのです。
そうした“変革の芽”を見つけ、育て、組織全体へと広げていく。それが私の支援のスタイルであり、組織に変革の渦を巻き起こすための鍵でもあります。
支援対象は“変えていない”──変わったのは支援の景色
表面的な変化と変わらぬ理念の関係性
ここ数年、「対象が広がりましたね」と言われることが増えました。
確かに、以前は経営者や幹部層の支援が中心でしたし、今は新入社員や人事担当者とも多く関わっています。けれど、自分の中で「支援の軸が変わった」と感じたことは一度もありません。
本質は、「誰を支援するか」ではなく、「どういう未来に向かって支援するか」です。
経営者の思考を変えることも、現場の対話を育てることも、すべては組織がよりよく機能し、未来に向けて前進するための手段です。そのために関わる相手が、経営層であれ、新入社員であれ、本質は同じ。
では何が“変わった”のか。
それは、**支援する「景色」**です。
対象の広がりによって、現場のリアルな声を直接受け取り、これまで見えていなかった組織の奥行きや、変革の可能性により深く触れるようになりました。
この景色の変化こそが、私にとってはありがたい学びであり、支援者としての成長を促してくれています。そして、その変化がまた、次の未来づくりへとつながっていくのだと感じています。
これからの「Future Support」が目指す未来
組織づくり×未来づくりの展望とこれからの実践
Future Supportという名のもと、私がこれまで取り組んできたのは、「人を育てる」こと以上に、組織という場に変化を起こし、その先の未来をともに描いていくことでした。
これからは、ますますその姿勢が問われていく時代だと感じています。人と組織を取り巻く環境はめまぐるしく変わり、不確実性が増す中で、「何を正解とするか」ではなく、「何を問い続けられるか」が重要になってきました。
Future Supportがこれからも大切にしていきたいのは、どんな立場の人とも、対等に“未来”について語り合える関係性を築くことです。
新入社員と語る未来も、経営者と語る未来も、本質的には同じ土俵にあります。そこに上下も優劣もありません。むしろ、その多様な視点が重なり合うことで、組織全体に新しい風が吹き込まれるのです。
私はこれからも、「誰か一人の変化が、組織全体を変えていく」という希望を信じて、対話と実践の現場に立ち続けます。
そして、関わるすべての人たちと一緒に、“未来をつくる力”を育んでいけたらと思っています。