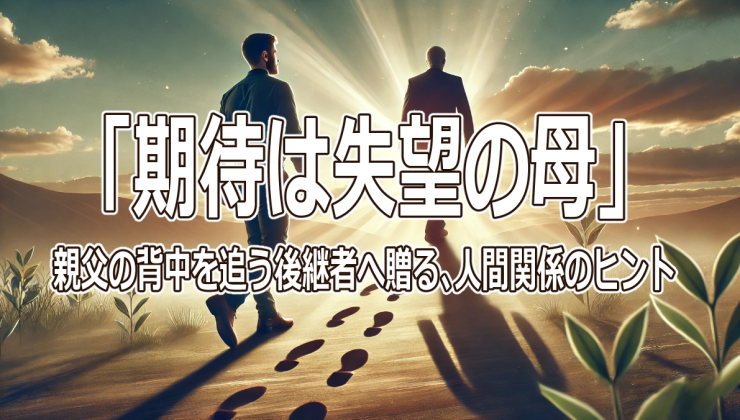「なんで?」
「やってクレナイ」
「思ってた通りにススメナイ」
相手になげき、苦しむ
不満を口にしてた、20代の自分
関係先の経営者が、救いの言葉をくださった
『期待は失望の母』
求めれば失う
対人関係はキタイでなく願うだけ
《求めるのは相手でなく、自分自身》ワタシの矢印、どこに向いてる?— ふさぽ@経営者 (@future_support) April 8, 2025
「やってくれない…」と悩んでいた若い頃の私
他責の気持ちに縛られていた20代
私が社会人としてのスタートを切ったのは、株式会社タナベ経営という経営コンサルティング会社でした。
全国の中堅・中小企業を対象に、現場に深く入り込む支援を行うという性格上、若手のうちから現場に立ち、経営者と直接対話する機会も少なくありませんでした。
20代の私は、自分なりに一生懸命でした。
クライアントのためを思って提案を重ね、社内でも改善策を声高に訴えていました。
ところが現実は、なかなか思い通りには進まない。
「なぜやってくれないのか」
「どうしてわかってもらえないのか」
「もっと協力してくれたらいいのに」
そんな“相手への不満”が、胸の中を渦巻いていたのです。
今にして思えば、当時の私は“他責の気持ち”にとらわれていたのでしょう。
自分ではなく、周囲が変わればうまくいく。そう信じて疑わなかった。
結果、仕事の手応えも人間関係も、次第に重たく感じるようになっていきました。
あの頃の自分が抱えていたのは、まさに「自分の矢印が外に向いていた」状態だったと思います。
そのことに気づかせてくれたのが、ある経営者のひと言でした。
経営者からの一言が変えた視点——『期待は失望の母』
心に深く残った、関係性を変える言葉
20代の私は、何かにつけて「不満」を口にしていました。
「言ったのに、やってくれない」
「思っていた通りに、進まない」
「なぜ、こっちの意図を汲んでくれないのか」
当時の私は、チームや関係者が自分の期待通りに動かないことに苛立ちを感じていたのです。
けれどその“期待”は、本当に相手の立場を思ってのものだったのか。
今思えば、それは自分の正しさを証明したい、思い通りにしたいという、独りよがりな気持ちだったのかもしれません。
あるとき、そんな私の姿を見ていた関係先の経営者が、ぽつりとこんな言葉をかけてくださいました。
「期待は失望の母やで」
その言葉は、まるで胸に鋭く突き刺さるようでした。
「思っていた通りにいかない」という苦しさの根っこに、自分の“期待”があるのだと気づかされた瞬間でした。
私は、知らず知らずのうちに「こうしてくれるはず」と周囲に期待し、その期待が裏切られるたびに、失望していたのです。
けれど、相手には相手の事情や考えがある。そもそも、“してくれるはず”という思い込みそのものが、関係性をこじらせていたのかもしれません。
あの時のひと言が、私の対人関係の向き合い方を、大きく変えるきっかけとなりました。
“期待”と“願い”は似て非なるもの
相手に求めすぎると、なぜ苦しくなるのか
「期待」と「願い」。
このふたつの言葉は、似ているようでまったく異なる意味を持っています。
“期待”は、心のどこかで「相手がこうしてくれるはずだ」という前提を含みます。
つまり、自分が描いた通りに動いてくれることを、無意識に“求めている”状態です。
そこには、自分の理想や価値観を相手に重ねてしまう危うさがあるのです。
一方、“願い”は違います。
「こうなったらいいな」「そうなってくれたら嬉しいな」と、心の中で静かに想うもの。
そこに“強制”はありません。結果がどうあれ、相手の意思や状況を尊重する余白がある。
願いには、手放す勇気と、信じる姿勢が含まれているのだと思います。
“期待”が裏切られれば、そこには失望が生まれます。
けれど、“願い”は裏切られても、誰かを責める気持ちにはなりにくい。
私が「期待は失望の母」という言葉に出会ったとき、真っ先に気づいたのは、
「私は、知らぬ間に“期待”を盾にして、相手を責めていたんじゃないか」ということでした。
対人関係において大切なのは、「願う」こと。
求めるのではなく、願い、信じ、そして委ねる。
その意識の違いが、相手との距離感や、関係の深まり方に大きく影響するのだと、今は強く実感しています。
本当に向き合うべきは、自分自身だった
自分の姿勢が変われば、関係も変わっていく
「人間関係がうまくいかない」と感じたとき、多くの人はまず“相手”に意識を向けます。
私自身もそうでした。動いてくれない相手に不満を持ち、理解されないことに苛立ちを感じていました。
けれどある時ふと、「もしかして、変わるべきは自分なのではないか」と気づいたのです。
きっかけは、自分の心の“矢印”がどこを向いているかに目を向けたことでした。
相手に向けていた矢印を、そっと自分に戻してみる。
「なぜ、私はそうしてほしいと思ったのか?」
「自分はどんな態度で接していたのか?」
「相手の立場に、きちんと想像力を持てていただろうか?」
そうやって自分に問いかけるようになったとき、少しずつ関係性が変わっていきました。
相手を“変えよう”とするのではなく、自分の“在り方”を整える。
すると、不思議と相手の反応も柔らかくなり、言葉の通じ方も変わってくるのです。
私が日々、後継者の方々と向き合うなかでもよくお伝えするのは、
「まず自分の矢印を見つめ直してみましょう」ということです。
変えられるのは、自分の意識と行動だけ。
そこに本気で向き合えたとき、人との関係は少しずつ、確かに変わりはじめます。
父の背中から学んだ「信じる」というリーダーシップ
相手を信じて任せることの大切さ
私はコンサルタントという立場ですが、これまで多くの“親から事業を受け継いだ後継者”と関わる中で、ある共通した悩みを耳にしてきました。
「父のようにはなれない」
「父のようなカリスマがない」
「つい、細かく指示を出してしまう」
それは裏を返せば、「自分の思う通りに動いてくれない不安」と、「相手を信じきれない迷い」からくるものでした。
そんな話を聞くたびに、私はある後継者のエピソードを思い出します。
その方は、先代である父から会社を引き継いだばかりの頃、まわりの動きが鈍く感じられ、すべてに口を出したくなっていたそうです。
ところがある日、ふと立ち止まって気づいたのです。
「そういえば、父はあまり細かいことは言わなかったな」と。
社員の動きに対しても、取引先とのやりとりでも、先代は多くを語らず、それでも会社は着実に前へ進んでいた。
それは、「信じて、任せていた」からこそ成り立っていたのだと、その後継者は気づきました。
信じるというのは、放任することではありません。
相手の可能性を信じて、必要な支援だけをし、あとは任せる――
それはとても勇気のいる行動です。けれどその“任せる強さ”こそが、信頼を育むリーダーシップの本質なのです。
私が出会ってきた多くのリーダーが、「口を出すより、見守る」ことの難しさと尊さを語ってくれました。
そしてその姿勢が、組織に芯のある自律性を育てていくのだと、私は確信しています。
矢印の向きが変わった時、人間関係も変わった
後継者に届けたい、これからの関係づくりのヒント
「矢印をどこに向けているか」
これは、私が今でも心の中に置いている問いです。
若い頃の私は、うまくいかないことがあると、すぐに“誰か”のせいにしていました。
けれど、「期待は失望の母」という言葉を受け取ったとき、初めて自分の内側に矢印を向けるという感覚を覚えたのです。
人間関係は、相手を変えようとするほどに、うまくいかなくなるものです。
でも、自分のあり方や視点が変わると、驚くほど関係性は変わっていきます。
不満をぶつける代わりに、まずは願う。そして、信じて、任せる。
その姿勢こそが、相手の本来持っている力を引き出す鍵になるのです。
後継者として、あるいはリーダーとして日々悩み、葛藤している皆さんにこそ、
この「矢印の向き」を見直す時間を持っていただきたいと思っています。
誰かに“求める”よりも、まず自分自身と向き合う。
そこから生まれる関係性には、無理がなく、芯があります。
矢印の先が他人でなく、自分に向いたとき。
人との関係は変わり始め、結果として組織も、未来も変わっていく――
私は、そう信じています。