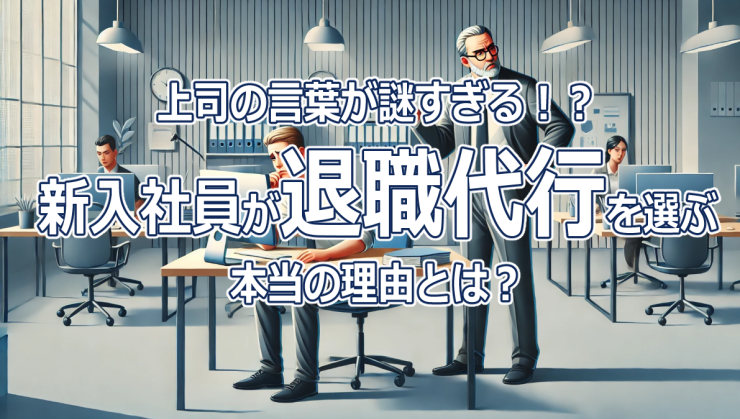実録!上司の意味不明発言!
①
上司「わからないことがあれば聞け」
依頼者「これがわからなくて…」
上司「そんなことぐらい自分で考えろ!」②
上司「今何をしてたんだ?」
依頼者「〇〇をしていて…」
上司「口答えするな!」③
上司「何も考えて仕事してないんだな」
〜考えて動く〜…— 退職代行モームリ (@momuri0201) March 28, 2025

X(旧Twitter)で話題になった「退職代行モームリ(@momuri0201)」さんの投稿には、
上司と部下の会話における“噛み合わなさ”が、これでもかというほど詰まっています。
今回は、「実録!上司の意味不明発言!」について深めてまいります。
退職代行モームリさんの投稿に見る、職場の“言葉のすれ違い”
上司の発言はなぜ理不尽に見えるのか?
上司:「わからないことがあれば聞け」
部下:「これがわからなくて…」
上司:「そんなことぐらい自分で考えろ!」上司:「今何をしてたんだ?」
部下:「〇〇をしていて…」
上司:「口答えするな!」上司:「何も考えて仕事してないんだな」
~考えて動いた結果~
上司:「なんでこんなことしてるんだよ、無能が」
このようなやり取りを見て、誰もが「理不尽すぎる」と感じるでしょう。
ですが、私自身、若いころにはこういう“曖昧な指導”を受けた経験がありますし、年を重ねて上の立場になったとき、無意識に似たような言い回しをしていたこともあるかもしれません。
つまりこの投稿は、ただの笑い話でも、上司批判でもない。
**言葉が通じていない現場の“リアルな苦しさ”**を象徴しているように思えるのです。
上司の側は「常識」「暗黙の了解」「阿吽の呼吸」といった、言葉にならない文化を前提に話しています。
一方で、部下の側は「聞くこと=責められること」だと感じてしまい、素直に動けなくなる。
こうしたすれ違いの根本には、言葉の定義や価値観のズレがあります。
一見すると理不尽な発言でも、そこに至った背景や心理を紐解いていくと、単なる「怒り」ではなく「伝わらない焦り」や「育て方がわからない不安」が滲んでいることも少なくありません。
退職代行という選択肢が注目されている今、このような投稿は
「一方的な怒り」ではなく「職場の限界点」が露わになった結果とも言えるでしょう。
新入社員の本音:「考えろ」と「聞け」の矛盾に戸惑う日々
若手が抱える“聞く恐怖”とコミュニケーション不全
新入社員にとって、職場での「正解のない会話」はとてもハードルが高いものです。
その中でも、「わからないことは聞け」と言われて聞いたら、「そんなこともわからんのか」と返される。
これは、一度でも経験してしまうと、もう次は聞けなくなってしまいます。
「聞いて怒られるなら、黙ってたほうがマシ」
そんなふうに考えてしまう若手社員は、いまや珍しくありません。
この背景には、単なる甘えではなく、“感情的に否定された経験”が心に残りやすいという構造があります。
人は、論理より感情のダメージを優先して記憶します。
たとえば、「ここをこう直せばよかったね」と冷静に言われるのと、「何考えてるんだ!」と怒鳴られるのとでは、後者の方が強烈に残るのです。
しかもその怒りが、「何を考えても否定される」ようなものだとしたら、ますます言葉が出なくなります。
結果として、職場では「黙る若手」と「苛立つ上司」の構図が生まれ、会話の断絶が進んでいきます。
本来ならば、若手は「なぜわからなかったのか」「どう考えたのか」を共有し、
上司はそれを受け止めてから、必要なアドバイスをするべきです。
でも、実際の現場では「時間がない」「忙しい」「教える余裕がない」という空気があり、
丁寧な対話よりも、短く強い言葉で指示を出してしまう場面が多くなっています。
この投稿に込められた戸惑いと諦めは、そうした背景から生まれた“聞くことの難しさ”を物語っているように思えます。
上司の本音:「教えること」が難しい時代背景
昭和・平成の「叱る文化」と令和のギャップ
多くの上司世代にとって、「教える」とは「叱ること」とほぼイコールでした。
昭和から平成にかけての職場では、「背中を見て覚えろ」「失敗して学べ」という文化が根付いており、仕事は“盗んで覚えるもの”という価値観が支配的だったのです。
このような時代を生きてきた人たちにとって、「何も考えてないのか?」という問いは、“怒り”というより“教育”の一環でした。
つまり、問い詰めることで考える力を促そうという意図だったのかもしれません。
しかし、令和の時代に入り、労働環境も価値観も大きく変わりました。
情報は“盗む”ものではなく、共有し合うもの。
そして、働く人の多様性が広がったことで、「同じ言い方がすべての人に通じるとは限らない」という認識が必要になっています。
にもかかわらず、上司の言葉が変わらない。
それは、**「教わっていないことは、教えられない」**という構造的な課題が根底にあるからです。
自分が若い頃に、丁寧に教えられた経験がないまま上司になった人は、「どう伝えればいいのか」がわからない。
だからつい、自分が言われた通りの“言葉”を繰り返してしまう。
これは、悪意や無関心からではなく、**「教育の連鎖が途中で断たれてしまった結果」**とも言えるのではないでしょうか。
さらに現代では、コンプライアンスやメンタルヘルスへの配慮が求められる一方で、
「厳しく言わなければ成長しない」という信念を捨てきれない上司も多い。
この揺れのなかで、伝えたいことを言葉にできず、結果的に誤解を生む場面が増えているのです。
「教えることが苦手な上司」は、実は、「教わることが少なかった人」なのかもしれません。
そんな背景に気づけたとき、部下としての視点だけでなく、同じ人間としての理解が深まるのではないでしょうか。
後継者の立場から見える“言葉”の重さと向き合い方
上司にも部下にも届く、言葉の選び方とは?
事業を継いだ立場、いわゆる「後継者世代」は、上と下、両方の気持ちがわかる特別なポジションです。
親の代を見て育ち、昔ながらの価値観や文化を知っている一方で、現場には若手社員もいて、彼らの感性や働き方にも直面しています。
この「どちらの立場にも共感できる」という感覚は、とても貴重なものです。
けれど同時に、「どう伝えるべきか」「どう理解すればいいのか」と悩む場面も少なくありません。
上の世代が使ってきた言葉は、時として強く、荒々しく、曖昧です。
「常識やろ」「それぐらい気づけ」という言葉には、ルールの共有よりも“察してほしい”という空気が漂います。
しかし、若手世代はその空気を読み取る訓練を受けていません。
正確な言葉で説明してもらえなければ、動くに動けず、萎縮するか、離れていくしかないのです。
だからこそ後継者世代は、“翻訳者”のような存在としての役割が求められます。
古い価値観をそのまま押しつけるのでもなく、若手の考え方にただ合わせるのでもなく、
それぞれの思いを「言葉にしてつなぐ力」が問われているのです。
たとえば、「これぐらい考えて動け」は、「どう考えて行動したのか聞かせてほしい」に変えられます。
「なんでこんなことしたんだ」は、「この判断に至った理由を教えてくれる?」に言い換えられます。
言い方ひとつで、人は“責められている”と感じるか、“信頼されている”と感じるかが変わる。
その違いを知っているのが、現場を預かるリーダーであり、後継者なのだと思います。
「言葉の重さ」とは、決して“威圧”のことではありません。
相手の心に届き、行動を促すための“温度”や“距離感”のことです。
それを意識できるかどうかが、これからの時代におけるリーダーの鍵になるでしょう。
退職代行を選ぶ前に、伝える工夫と聴く力を育てたい
すれ違いの芽を摘む、後継者世代の心がけ
退職代行という選択が、今の若い世代にとって“最後の逃げ道”ではなく、“最初に浮かぶ手段”になってきている。
これは、単に若者の忍耐力が落ちたからでも、世の中が過保護になったからでもないと、私は思います。
職場という場で、ちゃんと話せる相手がいない
そう感じる瞬間が続くと、人は自然と距離を置くようになります。
それが「退職」という形で表れる前に、私たちは何ができるのか――
それこそが、今、後継者世代に問われているテーマではないでしょうか。
若手は、自分の感情をうまく言葉にできないこともあります。
そして、上司はその言葉にならない部分を「甘え」や「不満」と捉えてしまいがちです。
だからこそ必要なのは、「言葉にできない気持ち」を汲み取ろうとする姿勢と、
「伝わるように話す」ための努力なのです。
後継者として、経営を預かる身になればなるほど、
数字や効率の話だけでなく、“人の感情”にも時間を割かねばなりません。
無駄に思えるような雑談、聞き流してしまいそうな小さな発言の中に、
「辞めたい」「苦しい」「わかってほしい」というサインが隠れていることがあります。
また、伝える側としても、「これぐらい言わなくてもわかるだろう」と思い込まず、
意識的に“補足する言葉”や“丁寧な確認”を添える工夫が求められます。
結局のところ、職場におけるすれ違いの多くは、言葉の量が足りていないことに起因しています。
だからこそ、私たちができることは、
少しだけ「話す勇気」を持ち、少しだけ「聴く余裕」を作ることではないでしょうか。
退職代行を使わなければならないような職場ではなく、
「この人には話してみよう」と思ってもらえる上司になる。
その小さな積み重ねが、今後の職場の空気を、そして会社の未来を変えていくと私は信じています。